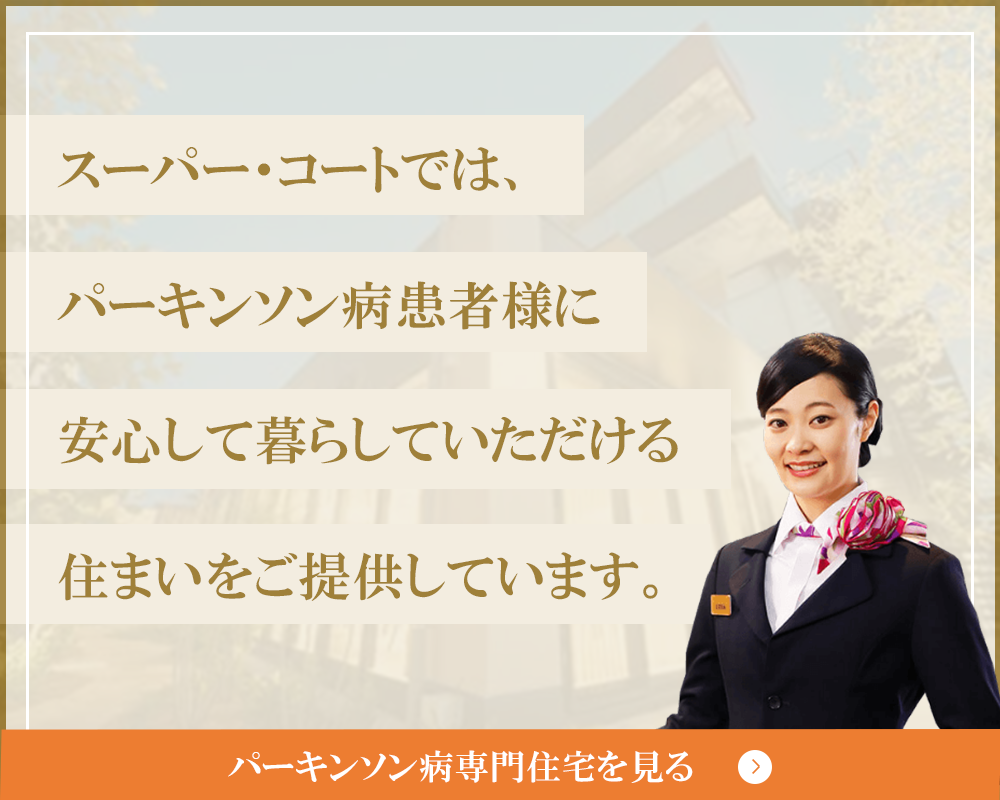column
コラム
公開日: 更新日:
パーキンソン病の治療で薬を飲まない場合の影響を解説

パーキンソン病の薬には、つらい副作用を引き起こしてしまうものがあります。
また、糖尿病などを併発していると必然的に薬の量が増えるため、「服用する量を減らしたい」と思う方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、自己判断で薬の量を減らしても問題ないのでしょうか。
本記事では、パーキンソン病の方が薬を減らす場合の注意点を解説します。
現在パーキンソン病の治療を行っており、副作用にお悩みの方はぜひご一読ください。
パーキンソン病を発症する原因
パーキンソン病の薬について知る前に、そもそもどういった原因で発症する病気なのかを把握しておきましょう。
パーキンソン病は、中脳にあるドーパミン神経細胞が減少することで、ドーパミンの生成量が不足するのが原因とされています。
ドーパミンは、意欲、幸福感、運動機能の調節といった脳機能に関わる神経伝達物質です。
パーキンソン病を発症すると、ドーパミンの不足により運動機能を調節するための脳の指令がうまく伝わらなくなり、さまざまな症状が表れます。
残念ながら、ドーパミン神経細胞が減少する正確な理由は分かっていません。
ただし、薬での対症療法によって症状を緩和させることができます。
パーキンソン病の主な症状
パーキンソン病を発症した方には、主に以下の4つの症状がみられます。
【パーキンソン病の方が発症する4つの症状】
- 振戦
- 筋強剛
- 運動緩慢
- 姿勢保持障害
これらは運動症状というものにあたり、手足の震えや筋肉のこわばりなどを発現するのが特徴です。
また、このほかに精神症状や自律神経障害などの、心身に不調をきたす非運動症状も発症します。
非運動症状は、運動症状に先立って発症する可能性が高いため、パーキンソン病を早期に診断するうえでの重要なサインとなっています。
パーキンソン病の重症度
パーキンソン病の重症度を表す指標には、一般的に「ホーエン・ヤールの重症度分類」が用いられます。
ホーエン・ヤールの重症度分類は1~5度まであり、それぞれ以下のような症状ごとに分類されます。
ホーエン・ヤールの重症度分類について
| 分類 | 症状 |
| 1度 | 片足にのみ症状が出る |
| 2度 | 両方の手足に症状が出る |
| 3度 | 姿勢保持障害も発症する |
| 4度 | 日常生活において部分的な介護が必要となる |
| 5度 | 車椅子での生活や寝たきりの生活となる |
パーキンソン病の患者さまで、重症度3度以上に該当する方は、難病医療費助成制度の対象です。
こちらに該当すると、診療の自己負担額が医療費の2割まで、または自己負担上限額までとなり、それ以上の費用は助成してもらえます。
パーキンソン病の治療で用いられる薬

パーキンソン病の治療では、症状の緩和を促すためにさまざまな薬が用いられます。
以下の表に記載したような、不足しているドーパミンを補う薬や、つらい運動症状を軽減させる薬などを使用するのが一般的です。
パーキンソン病の治療で用いられる主な薬
| 薬の名称 | 効果 | 副作用 |
| L-ドパ(レボドパ)製剤 | 脳内で不足しているドーパミンを補う | 運動合併症(※1) |
| ドーパミンアゴニスト | ドーパミンの作用を補い、症状の改善を目指す |
|
| MAO-B阻害剤 | ドーパミンを脳内で分解してしまう酵素であるMAO-Bのはたらきを抑え、ドーパミンの量が減少するのを防ぐ |
|
| カテコール-O-メチル基転移酵素阻害薬 | ドーパミンのもととなる物質L-ドパを分解してしまうCOMTのはたらきを抑え、L-ドパを黒質に届けやすくする |
|
| レボドパ賦活剤 | 体内でドーパミンが作られるのを促進し、ドーパミンの効果をなくす成分を排除することにより、脳内のドーパミンを増やす |
|
| アデノシンA2A受容体拮抗薬 | アデノシンA2A受容体を阻害し、アデノシンのはたらきを抑え、ドーパミンとのバランスを保つ |
|
| ノルアドレナリン補充薬 | ノルアドレナリンを補充する |
|
| ドーパミン遊離促進薬 | ドーパミン神経からのドーパミン分泌を促進する |
|
| 抗コリン薬 | ドーパミンの減少で、相対的に作用が強まったアセルチルコリンのはたらきを抑える |
|
※1 運動合併症:身体が動かなくなる、前かがみになる、震えが出るなどの症状のこと
※2 ジスキネジア:自分の意思とは関係なく身体の一部が不規則で異様な動きをする現象のこと
※3 悪心:嘔吐の前に起こるむかつきのこと
※4麻痺性イレウス:腸管の動きが鈍くなり、排便が困難になることで発症する病気のこと
※5心悸亢進:普段は自覚しない心臓の鼓動を前胸部に感じる不快感のこと
このように、薬はパーキンソン病の症状を抑えてくれる一方、運動合併症やせん妄などの副作用を引き起こす可能性もあります。
治療のためには欠かせないものではありますが、副作用がつらそうな場合は、すみやかに医師に相談しましょう。
ただし、自己判断で急に服用をやめると重篤な副作用を引き起こす可能性もあるので、医師が判断する前に中止するのは避けてください。
パーキンソン病で薬を飲まないとどうなる?
パーキンソン病の治療を進める際、「薬の服用は必要なんだろうか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
パーキンソン病には、根本的な治療法は存在しません。
そのため、現状は薬物療法での症状の緩和が中心となります。
薬物療法を行うことにより、患者さまの多くに症状の改善が見込めます。
薬物療法で症状の改善を目指すにあたっては、医師が決めた用法用量を守ることが大切です。
ただし、なかには患者さまや介護者さまの判断で、服用を突然やめてしまうケースがあります。
服用をやめるとパーキンソン病の症状がさらに悪化するだけでなく、それとは別に高熱や意識障害などの副作用を引き起こしてしまいます。
ひどい場合は命に関わる可能性もあるので、自己判断で薬の服用を中止することは避けましょう。
もし薬の量や副作用などが気になる場合は、担当の医師に相談してみてください。
薬を用いない治療方法
パーキンソン病では、身体的な症状だけでなくメンタルの不調も併発することがありますが、その不調を改善する際には薬に頼らない治療法を利用できます。
具体的には、『TMS治療』『精神療法』『電気痙攣療法』が挙げられます。
以下の表に、それぞれの詳しい概要をまとめたので、ぜひご確認ください。
TMS治療、精神療法、電気痙攣療法の概要
| 名称 | 内容 | 副作用 |
| TMS治療 | コイルを頭に当てて磁力で脳神経細胞を刺激し、パーキンソン病を治療する |
|
| 精神療法 | 認知行動療法などのカウンセリングを行う | 病気や障害によって、症状が悪化する可能性がある |
| 電気痙攣療法 | 頭部に電気を流して、痙攣発作を誘発する(※重度のうつ病の方が対象となる) |
|
このように、それぞれの治療方法によってその内容や副作用は異なります。
したがって、治療を受ける際は医師と相談し、ご自身に合った治療方法を見つけることが大切です。
日常生活での注意点

パーキンソン病の症状は、主に運動症状と非運動症状の2種類に分類されますが、さらに細かく分けると、その内容は多岐にわたります。
これらの症状は、薬を飲むことで改善が可能です。
そのうえで、悪化させないために、ご自身と介護者さまの双方が日常生活で気をつけたいことがいくつかあります。
生活面や介護面で注意すべきこと
| 項目 | 内容 | 対策 |
| よだれ | パーキンソン病を発症すると、無意識に唾が飲み込みにくくなる 頭や体が前かがみになり、かつ口も開きやすくなるので、よだれが出やすくなる |
|
| 首下がり | 頭部がうつむいたように下がって、上がらなくなる |
|
| すくみ足 |
|
|
| 便秘 | 自律神経障害によって腸の動きが悪化することで、便が出づらくなる |
|
| 起立性低血圧 | 自律神経障害の一種で、立ち上がった際に収縮期血圧が低下することで、立ちくらみを起こすようになる | 横になった状態から一気に立ち上がらず、一度座った状態から立つ |
| 幻覚・妄想 |
|
|
| ドーパミン調節障害、衝動制御障害 |
|
薬の減量や、変更を医師に調整してもらう |
なお、パーキンソン病の薬のほかに、胃腸薬や自律神経に作用する薬を服用している方は注意が必要です。
これらのなかには、ドーパミンの伝達を阻害してパーキンソン病による症状を悪化させる薬が存在します。
上記の症状の対策とあわせて、現在医師から処方してもらっている薬の状況も、きちんと把握しておきましょう。
また、パーキンソン病の方は高い確率で嚥下障害も併発するといわれています。
嚥下障害を患った状態で薬を一気に飲み込むと、むせたり、誤嚥を引き起こしたりするおそれがあるので、一錠ずつ飲ませてあげることを心がけてください。
関連記事:パーキンソン病になりやすい性格と気を付けたい生活習慣
パーキンソン病と認知症の関係性
パーキンソン病の患者は、そうでない方と比べておよそ4~6倍の割合で認知症を併発しやすいと考えられています。
パーキンソン病を発症すると、身体が徐々に思うように動かなくなることで、家にこもりがちになってしまうものです。
これにより、活動時間が減少することで、記憶障害や判断力の低下を招き、『パーキンソン病認知症』を発症するのです。
症状の例として、簡単な買い物や薬の管理を複雑に感じてしまうといったことが挙げられます。
上記の症状が進行すると、薬の管理を行うことが面倒くさくなり、勝手に服用をやめるというケースも出てくるかもしれません。
もし、薬の管理を一人で行うのが難しくなった場合は、無理せず周りの方の助けを借りましょう。
また、パーキンソン病認知症の治療においては、通常の認知症と同様、できるだけさまざまなことに興味や関心をもって日々の生活を送ることが大切です。
テレビやラジオなどの適度な刺激も、治療の手助けとなります。
関連記事:仮性認知症とは?認知症との見分け方・チェックリスト・治療方法を紹介
パーキンソン病専門住宅をお探しならスーパー・コートへ
薬の服用を続けても症状の緩和がみられず、日常生活を送るのが困難になった場合は、有料老人ホームスーパー・コートへの入居をご検討ください。
スーパー・コートでは、パーキンソン病の患者さまに安心していただけるような『パーキンソン病専門住宅』を提供しています。
こちらは、建物の設計や介護の体制など、提供するサービスすべてがパーキンソン病患者さまの介護に特化したものです。
また、薬剤師が入居者さま一人ひとりに処方された薬を施設にまで運び、服用のタイミングも適切に管理するので、飲み忘れる心配はありません。
薬剤師と看護師が連携して服薬管理や投薬調整を行うので、入居者さまは安心して治療を受けることができます。
パーキンソン病は進行性の病気で、なかなか症状の改善が見込めません。
だからこそ、患者さまに最適なサービスを提供できる、スーパー・コートのパーキンソン病専門住宅への入居がおすすめです。
施設選びや介護にお悩みのかたはお気軽にご相談ください。
介護相談のプロがあなたのお悩みに寄り添い、最適な施設をご紹介いたします。
パーキンソン病の薬は、自己判断で服用を中止すると症状がさらに悪化する可能性がある
今回は、パーキンソン病の治療で用いられる薬や、薬を飲まなかった場合の注意点を解説しました。
パーキンソン病の方が服用する薬は、症状の改善が見込める反面、副作用を引き起こす可能性が存在します。
ただし、副作用を恐れるあまり自己判断で薬の量を減らしたり、服薬の時間をずらしたりすると意識障害を起こすほか、症状が重症化するケースもあるので注意が必要です。
薬を服用しても症状の改善が見込めない際は、有料老人ホームスーパー・コートへの入居をご検討ください。
適切なリハビリはもちろん、一人ひとりに合った服薬管理や投薬調整も行い、患者さまに安心していただけるような生活環境を提供します。
監修者

花尾 奏一 (はなお そういち)
介護主任、講師
<資格>
介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
<略歴>
有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。