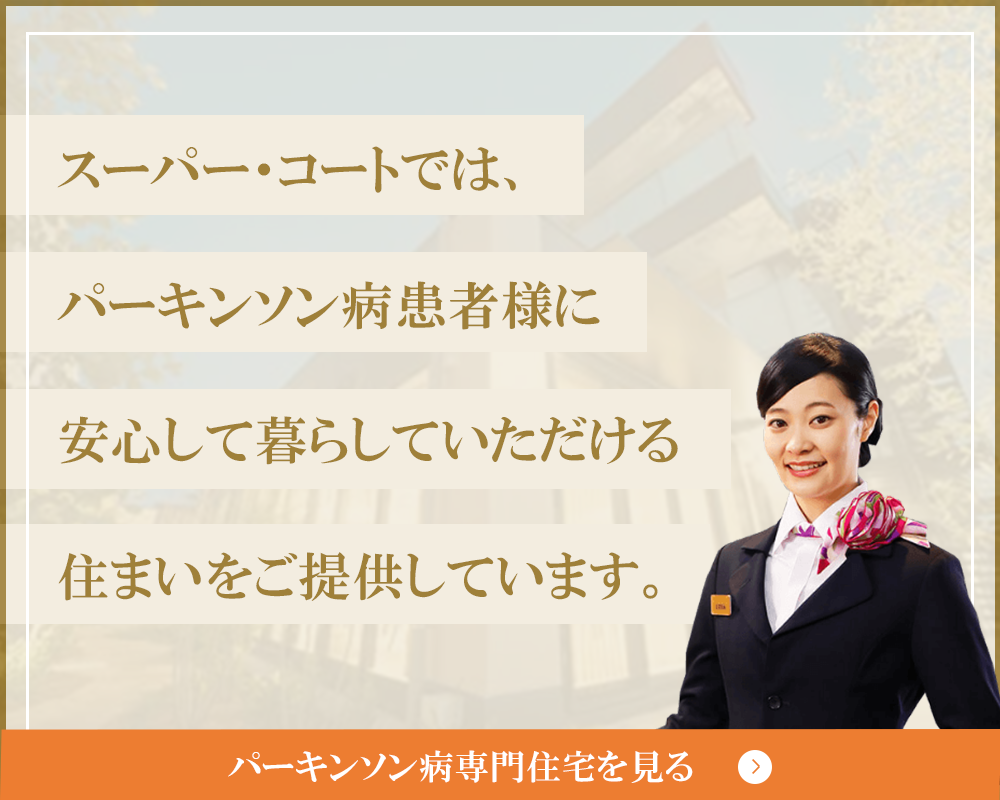column
コラム
公開日: 更新日:
パーキンソン病にみられる特有の歩き方とは?気になる場面と改善手法

パーキンソン病では歩幅が小さくなったり、すり足になったりするなど、特有の歩行障害が現れることがあります。このため、転倒のリスクが高まったり、日常生活に支障をきたしたりすることがあります。
ここでは「パーキンソン病と歩き方の関係について詳しく知りたい」と考えている方のために、押さえておきたいポイントを解説します。この記事では、パーキンソン病特有の歩き方や日常生活で注意すべき場面、改善方法について解説します。ぜひご覧ください。
パーキンソン病の主な症状
パーキンソン病では、さまざまな症状が現れます。なかでも以下4つの運動症状が代表的です。
【主な運動症状】
- 安静時振戦:ふるえ
- 動作緩慢:動作が遅く、小さくなる
- 筋強剛:筋肉のこわばり
- 姿勢反射障害:姿勢を保てなくなる
この中でも、初発症状として代表的なのが安静時振戦です。その後、細かい動作がうまくできなくなるなどの症状が現れることが少なくありません。
パーキンソン病では運動症状がよく知られていますが、精神症状や自律神経障害、感覚障害、睡眠障害がみられることもあります。
うつや疲労、嗅覚障害などが症状として現れることもあるため、なかなか「この症状が出たら病気の可能性が高い」というのは難しい病気です。
パーキンソン病になると変わる特有の歩き方
症状が進行すると、歩き方が変わることがあります。突進歩行と呼ばれるもので、歩く際に前のめりになり小走りの状態になるのが特徴です。
自分の意思では止めることができず、何かにぶつかったり、転んでしまったりすることもあります。
これは、パーキンソン病が筋肉に指示を出している脳の病気であることが理由です。正しく筋肉に命令できなくなり、突進歩行という歩行障害を引き起こします。
また、歩こうとしたときや、歩いている途中で突然足が止まってしまう「すくみ足」も代表的な症状の一つです。狭い場所での方向転換や、ドアの出入りなど特定の状況で起こりやすい とされています。
脚が地面にくっついてしまうような感覚になり、症状は数秒~数分間続きます。
転倒のリスクが高くなる非常に危険な症状です。
パーキンソン病によって歩き方が変わる確率
すくみ足は、発症した患者の約50%が経験すると報告されています。(※)
約半数であることから、必ずしもすくみ足の症状が出るとは限りません。ですが、症状が進行するにつれてすくみ足の有病率も高くなるとされているので、転倒リスクの管理や専門的なリハビリなど、早めの対策が必要です。
(※)
参考:(PDF)理学療法科学:内的リズム形成課題により歩行継続時のすくみ足の改善を示した進行期パーキンソン病患者の1症例[PDF]
パーキンソン病にかかって歩き方が変わる場面
病気によって突進歩行やすくみ足といった歩行障害の症状が現れることがありますが、常に異常があるわけではありません。
突進歩行の場合は歩行中に突然現れることもありますが、すくみ足は歩行開始時の1歩目や、方向転換の際に現れることがあるのが特徴です。
また、狭い道を通るときや、人とすれ違うとき、障害物をよけるとき、目標地点に到着する直前などでもすくみ足が発生しやすい傾向があります。
パーキンソン病特有の歩き方を改善する手法
すくみ足を改善する代表的な手法には、聴覚キュー、視覚キュー、行動観察療法、トレッドミルトレーニングなどがあります。それぞれ解説します。
手法①聴覚キュー
すくみ足が発生する原因の一つとして、パーキンソン病では歩行のリズムを作る能力が低下することが挙げられます。
そこで、外部から一定のリズムを提供することで聴覚を刺激し、歩行をスムーズにする「聴覚キュー」という手法が効果的とされています。
たとえば、メトロノームの音を聞きながら音に合わせて歩くトレーニングを行います。メトロノームの速度は、その人の歩行ペースに合わせて調整し、無理なくリズムに乗れるように設定することが重要です。
手法②視覚キュー
視覚キューとは、歩幅に合わせて一定感覚の線を引いてその上を歩くなど、目で見て行うリハビリ手法です。すくみ足の症状がある人は、歩く際に足が止まってしまうことがありますが、目印があるとスムーズに歩きやすくなることが知られています。
また、パーキンソン病の影響で歩幅が小さくなりやすいため、意識的に歩幅を広げることが重要です。歩幅が小さいと、ちょこちょことした歩行になり、バランスを崩して転倒しやすくなる可能性があります。
そのため、徐々に線の間隔を広げることで、安定した歩行を維持しながら、転倒リスクを減らすことを目指します。
手法③行動観察療法
行動観察療法とは、実際にすくみ足が発生してしまったときにどのように回避すればいいのかを動画で学ぶ方法のことをいいます。
特に行動観察療法が効果的とされているのは、1歩目で発生するすくみ足や、方向転換をする際に発生する、すくみ足です。正常な歩き方を動画で確認し、そのうえで同じ動作を行うトレーニングをします。
手法④トレッドミルトレーニング
トレッドミル(ルームランナー、ランニングマシン)は、屋内でウォーキングやランニングのトレーニングができる運動器具です。
パーキンソン病のリハビリでは、歩行リズムの改善や持久力向上を目的に使用されることが一般的です。
また、視覚キューや聴覚キューと組み合わせることで、歩幅やリズムの調整をしながら歩行練習ができます。
施設選びや介護にお悩みのかたはお気軽にご相談ください。
介護相談のプロがあなたのお悩みに寄り添い、最適な施設をご紹介いたします。
パーキンソン病は突進歩行・すくみ足に注意
いかがだったでしょうか。パーキンソン病では歩き方がどのように変わるのかを解説しました。歩き方の問題は転倒にもつながる恐れがあるので、医師だけでなく、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)などと相談しながら対策を取ることが重要です。
有料老人ホームスーパー・コートでは、パーキンソン病などの神経難病の方に特化した介護施設を運営しています。
運動機能の維持を目的とした取り組みも行っているため、ご興味のある方はぜひご相談ください。
監修者

花尾 奏一 (はなお そういち)
介護主任、講師
<資格>
介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
<略歴>
有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。