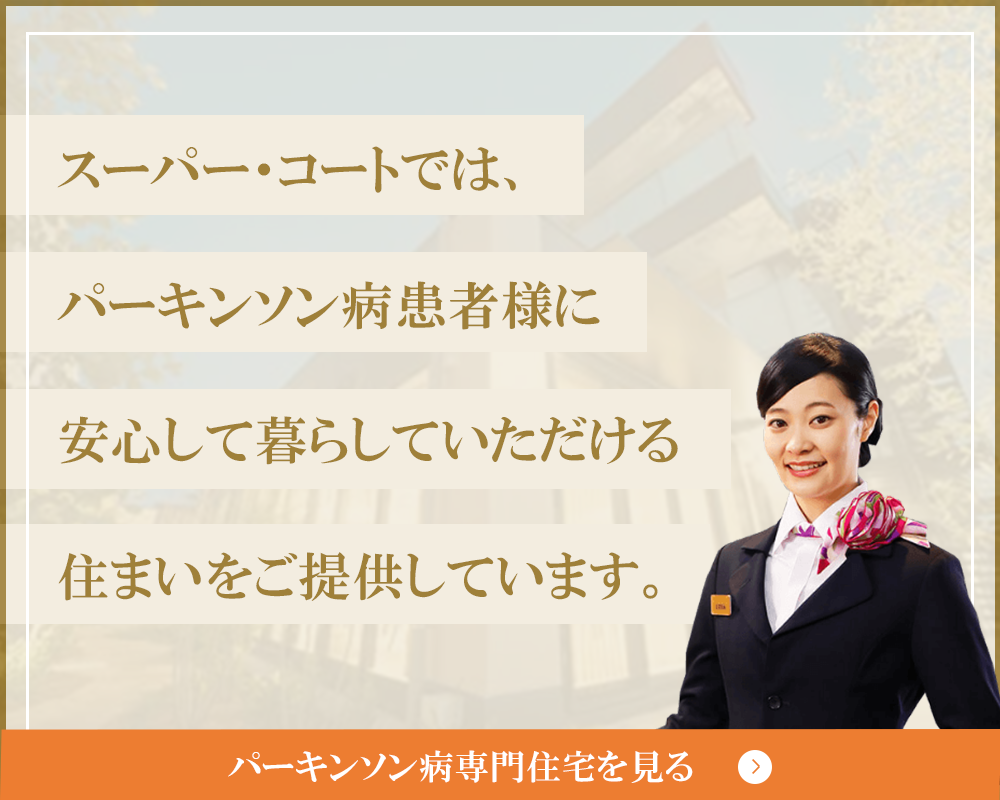column
コラム
公開日: 更新日:
パーキンソン病の方が抱えるトイレトラブルと対処法を解説

日本国内のパーキンソン病患者は年々増えつづけ、約1,000人に1人が発症しているといわれています。
パーキンソン病は発症するとさまざまな症状が身体に表れますが、とくに患者さまの約半数が悩まれているのが、排尿障害です。
そこで本記事では、パーキンソン病の自律神経症状であるトイレトラブルに焦点を当てて、その対処法を解説します。
使いやすいトイレの工夫も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
パーキンソン病とは
パーキンソン病は、情報伝達物質である「ドーパミン」が減少することで、脳の指令がうまく筋肉に伝わらなくなる病気です。
振戦(しんせん)、筋固縮(きんこしゅく)、姿勢反射障害が代表的な症状として表れます。
このような運動症状のほかにも、自律神経症状、精神症状、認知機能障害などの非運動症状もパーキンソン病の特徴です。
それぞれの症状については、詳しく後述します。
どんな人がパーキンソン病を発症しやすいのかについては、現在でもよく分かっていません。
主に50歳を過ぎると発症率が上がり、発症すると10年以上かけてゆっくりと進行していきます。
全体では1,000人に1人、65歳以上の高齢者に限ると100人に1人がパーキンソン病患者だといわれており、老齢人口増加に伴い、世界的に見ても増加傾向にあるのが現状です。
パーキンソン病の主な症状
パーキンソン病の症状は、身体の動きが制限される運動症状と、それ以外の非運動症状に二分されます。
【パーキンソン病の主な症状】
| 運動症状 | 非運動症状 |
| ●振戦(しんせん) ●筋固縮(きんこしゅく) ●寡動(かどう)・無動 ●姿勢反射障害 |
●自律神経症状 ●睡眠障害 ●認知・精神障害 |
以下から、それぞれの症状について詳しく見ていきましょう。
まずは、運動症状から解説します。
振戦(しんせん)
パーキンソン病患者の方の特徴的な症状といえば、振戦とよばれる手足の震えです。
片方の手や足から震えが始まることが多く、通常はじっとしている安静時に起こります。
一方で、手や足を意図的に動かしているときはあまり見られず、就寝中に至ってはまったく起こりません。
筋固縮(きんこしゅく)
筋肉が固くなって動くことが困難になる筋固縮の症状では、腕や脚を曲げたり伸ばしたりしようとすると、関節がカクカクするような抵抗が感じられます。
このような筋肉の硬直と関節の可動域の低下により、寝返りを打つこと、立ち上がること、車の乗り降りなどの動作が困難になっていきます。
そして次第に手先の筋肉すら制御できなくなり、シャツのボタンをかける、靴紐を結ぶなどの細かい動作も困難となり、日常生活にも支障をきたし始めるのです。
また、顔面の筋肉をコントロールすることができなくなるため、表情が乏しくなります。
症状がさらに進行し、のどの筋肉も固くなって飲み込むことが困難になると、食事を詰まらせたりするので、この段階になると全面的な介護が必要です。
寡動(かどう)・無動
パーキンソン病を患った方は、素早い動きができません。
歩行時には、速度がゆっくりとなるだけでなく、足が前方に出にくくなるので(すくみ足)、歩幅も小さくなります。
また歩行時だけでなく、会話中の口の動きにもこの症状が表れ、話し方がゆっくりと、さらに抑揚のない小さな声になります。
パーキンソン病の方が書く文字も、特徴的です。
手の震えや指先のこわばりがあるため、字の一画一画を書くことが難しく、本人の意思とは反して文字が極端に小さくなっていきます(小字症)。
これらはすべて、脳から筋肉へうまく信号が伝わらないため、身体のいたるところが動かしにくくなってしまうことが原因です。
姿勢反射障害
姿勢反射障害が起きると、平衡感覚を保てなくなるので、前方や後方に倒れるようになります。
しかし、動作がゆっくりのため、転びそうになってもさっと手をつくことができません。
当たり所が悪い転倒は、骨折の原因になることもあるため注意が必要です。
姿勢反射障害は病気の後期に見られることが多く、進行すると、首が下がったままになったり、身体が斜めに傾いたりすることがあります。
続いて、非運動症状について見ていきます。
自律神経症状
パーキンソン病では、脳のほかに中枢神経や自律神経もダメージを受けます。
パーキンソン病による自律神経症状の代表的な症状は、便秘です。
腸の内容物を送る動きがゆっくりとなるのが理由で、患者さまのおよそ80%に症状が出ます。
そのほかにも、排尿障害、起立性低血圧(たちくらみ)、食事性低血圧(食後のめまいや失神)、発汗、むくみなどの症状に悩まされることもあります。
このなかでも、本記事のテーマであり、パーキンソン病の方の約半数が悩んでいるとされる排尿障害については、のちに詳しく解説していますのでご覧ください。
睡眠障害
パーキンソン病では、さまざまな睡眠障害が病気の初期からみられます。
例を挙げると、不眠、レム睡眠行動異常症、むずむず脚症候群、夜間頻尿などで、これらが原因となって断続的な睡眠が阻害されるので、深い眠りに就くことができません。
パーキンソン病患者の方の40%にこの現象がみられ、病状が進行するとその頻度は増加します。
なお、この症状は、パーキンソン病の治療薬の副作用として表れる場合もあります。
認知・精神障害
パーキンソン病で出現する精神障害の一つである抑うつは、発症する方の割合が多く、病気が進行するに伴って徐々に悪化していきます。
具体的には無気力状態(アパシー)に陥って身の回りのことに関心が無くなったり、不安状態が続いたりしてふさぎ込むようになります。
また、高齢の患者さまのなかで認知症を併発した方に表れるのが、幻覚や妄想の症状です。
薬による治療も行われますが、この段階になると施設などに入居して、全面的な介護を必要とする患者さまが多くなります。
関連記事:パーキンソン病が進行する流れと注意しておきたい運動合併症
パーキンソン病の排尿障害とその症状

非運動症状を解説した際にも少し触れましたが、パーキンソン病の自律神経症状の一つに「排尿障害」があります。
ここからは、パーキンソン病による排尿障害にはどのような症状があるのかを、具体的に見ていきましょう。
頻尿
1日に8回以上の短い時間間隔でトイレに行きたくなることを、頻尿といいます。
パーキンソン病では脳の神経回路で異常が起きるため、膀胱にたまっている尿が少ないにもかかわらず、排尿するように脳から指令が出ます。
その結果、何度もトイレに行くことになるのです。
速やかな移動が難しいので、トイレまで間に合わずに失禁してしまうこともあります。
排尿困難
排尿困難とは、尿意をいざ感じても思うように排尿できない状態です。
この症状の原因は、尿道括約筋という筋肉の運動障害です。
パーキンソン病では蓄尿する機能だけでなく、次第に排尿する機能も失われていきます。
同時にこれらの症状が出て排尿自体が困難になると、改善するためのアプローチが複雑化する傾向にあります。
尿失禁
尿失禁では、蓄尿から排尿を調節する筋肉のはたらきがうまくいかないため、コントロールできずに尿が漏れてしまいます。
失禁は精神的ダメージが大きく、患者さまのみならず介護者の負担も大きくなります。
身体をスムーズに動かせないと焦る気持ちから、症状がさらにひどくなる傾向にあるため、尿取りパッドやポータブルトイレを用意するなど、早期の対策が必要です。
パーキンソン病の方のトイレトラブルへの対策
パーキンソン病でのトイレトラブルは、主に薬物療法である程度改善することができます。
原因によってアプローチの仕方が異なるので、以下から詳しく見ていきましょう。
過活動膀胱が原因の場合
過活動膀胱が原因の場合に利用されるのが、ドーパミン薬です。
一定期間内服することで、膀胱排尿筋の過活動性に対して効果を発揮し、頻尿や失禁が改善することがあります。
薬物療法だけでなく、行動療法として利尿作用のある飲み物を意識的に避けることも効果的です。
アルコールやカフェインには利尿作用があるだけでなく、睡眠にも影響を与えるため、夕方以降はとくにこれらの飲み物は避けましょう。
睡眠障害が原因の場合
睡眠障害によって頻尿などのトイレトラブルが起きている場合は、睡眠剤を使用して、深く眠りにつける環境を作ります。
睡眠障害が頻尿の原因になったり、その逆に頻尿のため夜中に何度も起きることが睡眠障害につながったりします。
こうした悪循環を薬で断ち切り、熟睡できるようにすることが、頻尿を改善させることにつながるのです。
パーキンソン病の方が使いやすいトイレの整備とは
狭い空間では、転倒リスクが高くなります。
とくにトイレでは、身体を安定させたり、方向転換することが難しくなったりするため、以下を参考にしてパーキンソン病患者の方が使いやすいトイレを作りましょう。
なお、国の介護保険を利用すれば、介護リフォームのための補助金を受け取ることができるので、気になる方は調べてみるとよいかもしれません。
ひじ掛け付きの手すりを設置する
ひじ掛け付きの手すりであれば、体重を預けもたれ掛かることができるので、動作に安定感が生まれます。
パーキンソン病による筋肉の硬直が起こるのは、背中も例外ではありません。
背中の筋肉が硬直すると身体がひねりづらくなるので、便座の上で姿勢が崩れバランスを失うおそれがあります。
このときに、ひじ掛け付きの手すりがあれば安心です。
その際は、はねあげ式ではなく、身体を大きくひねらなくても届きやすいスライド式を採用するとなおよいでしょう。
なお、L字型の手すりのみの設置は、ふき取り時や着脱時に片手がふさがってしまうため、おすすめできません。
引き戸にし、段差を解消する
開き戸のトイレは、開ける際に扉が手前に開くので、後ずさりする必要があります。
パーキンソン病患者の方は、身体がスムーズに動かないだけでなく、方向転換も苦手なため、ふらつくとそのまま転倒へとつながります。
そこで、採用したいのがスライド式の引き戸なのです。
開き戸の場合は、後ずさりしなくてもよい立ち位置をあらかじめ床にマークしておくのが分かりやすくてよいでしょう。
また、パーキンソン病患者の方は脚が前に出にくく、すり足のように歩くため、段差につまずきやすくなります。
ドアと床のあいだにある段差を取り除き、フラットするのが理想です。
車椅子になっても、スムーズに対応できるところが、段差がないことの最大の利点です。
暖房便座にする
便座が冷たいと筋肉が余計動きづらくなるため、暖房便座にするのもおすすめです。
冬場の寒い時期には便座だけでなくヒーターも稼働し、空間全体を温めておくのが、急な寒暖差を防ぐためにも大切です。
トイレにヒーターが設置されていない場合は、トイレや脱衣所用の小型ヒーターを購入するとよいでしょう。
関連記事:パーキンソン病の方が使いやすいトイレの整備とは
パーキンソン病は発症からどのような経過をたどる?
ここまでで、パーキンソン病の主な症状を詳しく解説しましたが、「こんなに症状があると、先は長くないのかも……」と感じた方もいらっしゃるでしょう。
しかし、そこまで悲観する必要はありません。
パーキンソン病は現在、治療薬が研究開発されており、平均寿命は全体とほとんど変わらないといわれています。
進行性の病気であることは変わりませんが、予後は決して悪くありません。
もちろん、転倒による骨折や、便秘による腸閉塞、食事の際の誤嚥性肺炎のリスクには気をつける必要はあります。
また、対処療法ではあるものの、パーキンソン病は薬の投与によってうまくコントロールできる病気の一つです。
「発症すると、10年後には確実に寝たきりになる」といわれたのは、すでに過去の常識です。
仮に、長い闘病生活を余儀なくされた場合も、在宅医療や介護サービスをうまく利用すれば、ご家族の精神的ストレスも軽減できます。
高齢化社会が進む日本では、今後否応なく、老老介護のケースが増えていくと思われます。
周りのサポートはできる限り利用して、あまり肩ひじを張らずにパーキンソン病に向き合っていきましょう。
施設選びや介護にお悩みのかたはお気軽にご相談ください。
介護相談のプロがあなたのお悩みに寄り添い、最適な施設をご紹介いたします。
パーキンソン病の抱えるトイレトラブルは、薬物療法で改善できる

本記事では、パーキンソン病の主な症状にくわえて、自律神経障害の一つであるトイレトラブルに焦点を当てて解説しました。
パーキンソン病患者の方が抱える頻尿や排尿困難は、薬によって改善が期待できます。
またトイレに肘掛け付きの手すりを設置し段差をなくすことで、動作が安定します。
症状が進行して、全面的な介護が必要になったら、在宅医療や介護サービスを積極的に活用してサポートを受けることも大切です。
有料老人ホームスーパー・コートは、パーキンソン病の介護に特化した専門住宅です。
パーキンソン病の知識や経験が豊富なスタッフが、患者さまに合った最適な介護を提供いたします。
監修者

花尾 奏一 (はなお そういち)
介護主任、講師
<資格>
介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
<略歴>
有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。