
column
コラム
公開日: 更新日:
パーキンソン病の方でも特養に入居できる?入居の条件を解説

パーキンソン病を患うと、日常生活が困難になるため周囲のサポートが不可欠です。
場合によっては、在宅介護では足りず、介護施設の利用も検討する必要があるかもしれません。
なかでも、特別養護老人ホーム(特養)なら低料金で手厚い介護を受けられるため、ご家族も安心できるはずです。
そこで本記事では、パーキンソン病の方が特養に入居する際の条件をお伝えします。
大切なご家族の穏やかな生活を願う方は、ぜひご覧ください。
特別養護老人ホーム(特養)の概要
特別養護老人ホーム(特養)とは、病気や障害などで、在宅での生活が困難になった高齢者が入居できる公的施設のことです。
厚生労働省が定める老人福祉法により、以下のように定義されています。
特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
( 引用:厚生労働省 老人福祉法)
上記の法令に則って、特養では主に入浴や食事の介助といった日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話などを提供しています。
また、一部の施設では24時間体制で介護支援を実施しているため、食事や夜間のトイレなどに補助が必要なパーキンソン病の方でも受け入れ可能です。
とはいえ、“特別養護”という言葉のとおり、すべての高齢者が入居できるわけではなく、一定の条件を満たす要介護者しか入居できない決まりとなっています。
この条件については、次の項で解説します。
特養に入居できる条件
ここからは、特養に入居するにあたって必要となる条件をお伝えします。
ほとんどの老人ホームにいえることですが、特養も例に漏れず、入居者に対して年齢制限が設けられています。
くわえて、介護保険制度に基づいて認定される「 要介護度」も条件に含まれ、これらを満たした要介護者が入居できるわけです。
要介護度は1~5に分けられており、この数字が入居の可否を決める基準となっています。
特養の一般的な入居条件は、「要介護度3以上かつ、65歳を超えた高齢者」であることです。
しかし、パーキンソン病を含む「特定疾病」を患う方や、「特例」に該当する方はその限りではありません。
以下で、特定疾病と特例に該当する方の入居条件を深掘りしていきます。
関連記事:パーキンソン病施設の選び方や入居条件・費用相場と公的支援制度
“ 特定疾病”と認められた要介護度3以上で40歳以上の方
要介護度3以上で、厚生労働省が認める16の「特定疾病」の対象であれば、40~64歳の方でも特養に入居できます。
特定疾病とは、加齢に伴って心身に変化が生じ、いずれ要介護状態に陥る可能性の高い病気のことで、パーキンソン病はこれに該当します。
パーキンソン病の罹患者は、大半が50~65歳だといわれていますが、40歳前後で発症するケースも少なくありません。
発症後は、手足の震えや嚥下障害、排尿障害などの症状が表れ、それがさらに悪化すると食事や排泄を一人で行うのも難しくなります。
つまり、日常生活全般におけるサポートが必要で、24時間体制での見守りや介助が欠かせなくなるわけです。
ご家族にパーキンソン病を患っている方がいる場合は、お住まいの市区町村の窓口に要介護認定の申請をしたうえで、特養への入居を検討してみてください。
その際、特養は入居希望者が多く、順番待ちが発生するケースがほとんどなので、パーキンソン病という特殊事情を話し、優先的に入居させてもらえる施設を探しましょう。
要介護1~2で“特例”に該当する方
特養に入居するには、原則として要介護度が3以上であることが条件とお伝えしましたが、要介護度1~2と認定された方でも、下記の特例に該当すれば入居できます。
ただし、これはあくまでも「特例」なので、パーキンソン病を含めた特定疾病の対象者は該当せず、特養への入居は要介護度3以上でなければなりません。
以下で、要介護度1~2の方が特養への入居を認められる特例の詳細をご確認ください。
【要介護度1~2の方が特養への入居を認められる特例】
- 認知症の進行により、日常生活が困難になっている
- 知的障害や精神障害により日常生活に支障をきたしている
- 同居家族から虐待を受けており、生活できる環境ではない
- なんらかの理由で家族や地域からの十分な支援を期待できない
上記の内容から、特養では心身の病によって日常生活を満足に送れない方や、家庭環境に問題を抱える方も受け入れているのが分かります。
特養は、「地域のセーフティネット」としての役割も担っているのです。
特養に入居することのメリット
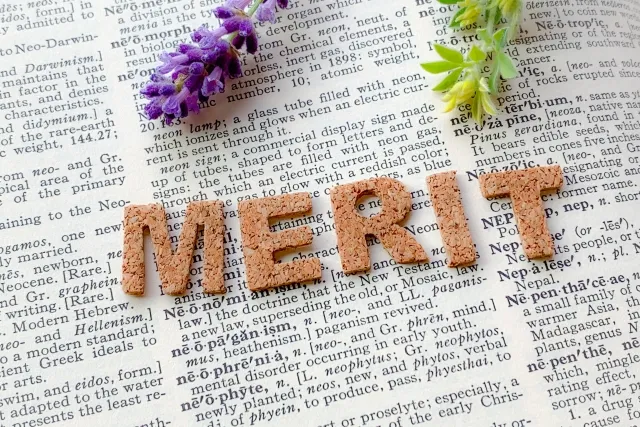
パーキンソン病の方でも、「要介護度3以上で40歳以上」という条件を満たせば特養に入居できることがお分かりいただけたでしょうか。
ここからは、特養への入居で得られるメリットを3つ紹介します。
メリット①費用が安い
特養を利用するメリットとして、一般的な老人ホームと比べて費用が安いことが挙げられます。
民間が運営する有料老人ホームでは、月額利用料だけではなく入居一時金も必要で、初期費用が数十万~数百万円、場合によっては数千万円と高額になりがちです。
その点、国から運営助成金が支給される特養なら、格段に低料金で介護サービスが受けられるのです。
月額利用料の安さにくわえて、入居一時金も不要というのですから、年金生活者やそのご家族にとって、経済的恩恵がいかに大きいのかは明白でしょう。
メリット②24時間介護を受けられる
多くの特養では、24時間体制で介護職員が常駐しており、昼夜問わず介護支援を受けられます。
パーキンソン病を患うと、身体を思うように動かせなくなり、食事や排泄にも大変な苦労を伴います。
そのようなとき、すぐに駆けつけてくれる介護職員が近くにいるということが、ご本人にとってどれだけ心強いかは容易に想像できるのではないでしょうか。
また、パーキンソン病は夜間でも症状が悪化する可能性があるため、万全な介護体制が整っていれば、ご本人はもちろんご家族も安心できるはずです。
メリット③原則的に終身まで利用できる
介護が必要な方にとって「終の棲家」となる特養は、長期の入居が可能です。
一部の老人ホームでは、あらかじめ入居期間を設けているケースがあり、その期間を過ぎたら退居しなければなりません。
しかし、特養は原則として終身までご本人に寄り添ってくれるため、ご家族は何度も施設を探す手間が省けて、ご本人との時間をゆっくりと過ごせます。
また、パーキンソン病は昼夜を問わず周囲の方のサポートが必要なので、介護で疲弊したご家族が体調をくずしてしまうことも少なくありません。
そのような事態を避けるためにも、長く入居できる特養を利用して、介護者自身も適度に心身を休めることが重要なのです。
パーキンソン病の方が快適に過ごせる特養の選び方
パーキンソン病の症状が進むと、手足の震えやバランス障害が顕著に表れるため、いつ転倒事故が起こってもおかしくない状態に陥ります。
また、身体への影響だけではなく、メンタル面にも変化が生じて、気分の落ち込みや意欲の低下が見られるようにもなります。
以上のことを踏まえて、パーキンソン病の方が入居する特養は、以下の条件がそろっているかどうかを基準に選んでみてください。
【パーキンソン病の方が入居する老人ホームを選ぶ際のポイント】
- 手すりの設置や段差の解消による安全性が担保された住環境が整っている
- パーキンソン病の症状を理解しているスタッフが在籍している
- 適切な生活リズムをつくるサポートをしてくれる
- 運動療法を適度に取り入れている
- 時間がかかってもできることは本人の力で行うようサポートしてくれる
これらはあくまでも一例として捉え、ご本人とご家族の双方が納得できる施設を慎重に選ぶことが大切です。
関連記事:パーキンソン病の方を施設に入れたいときに押さえておきたいポイント
パーキンソン病の方が受けられる主な支援制度
国が設ける制度のなかには、パーキンソン病の方が支援を受けられるものがあります。
以下で、主な支援制度を3つ紹介します。
難病医療費助成制度
パーキンソン病を患っている方は、医療費の一部を国に負担してもらえる、難病医療費助成制度の対象となる場合があります。
パーキンソン病の重症度を測る際には、「ホーエン・ヤール重症度分類」「生活機能障害度分類」という特有の指標が用いられます。
前者は1~5度に、後者は1~3度に分類されており、「ホーエン・ヤール重症度分類3度以上かつ生活機能障害度2度以上」の方は、難病医療費助成制度の対象です。
ただし、この基準を満たしていなくても、毎月の医療費総額が3万3,330円を超える月が年間3回以上ある方も助成対象と認められます。
助成を受けるためには、各市区町村の窓口に必要書類を提出する必要があり、認定されると指定難病医療受給者証と、自己負担上限額管理票が交付されます。
この自己負担上限額管理票に記載された、1か月の自己負担上限額を超えた部分の医療費が支給されるわけです。
介護保険制度
40~64歳で、パーキンソン病の治療に介護が必要と認定された方は、介護保険制度を利用できます。
介護保険制度では、原則として65歳以上の要介護認定、あるいは要支援認定を受けた被保険者が介護サービスを受けられます。
しかし、パーキンソン病をはじめとする特定疾病を患っている場合は、65歳未満でも支援対象となるのです。
この制度によって、該当者は介護施設への入居費用をはじめ、訪問介護や訪問リハビリテーションといった介護サービスを、1~3割程度の自己負担額で利用できます。
自己負担額の割合は、必要な介護の度合いやご本人の所得、年金収入の額によって決定されます。
身体障害者福祉法
パーキンソン病の発症に伴い肢体が不自由になった方は、身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳が交付され、さまざまな支援を受けられます。
ただし、症状の程度によってはこの法律が適用されず、援助や保護の対象とならないケースもあるので注意が必要です。
身体障害者手帳が交付されたパーキンソン病の方が受けられる主な支援は、以下のとおりです。
【身体障害者福祉法によって受けられる主な支援】
- 経済的な支援(医療費の助成、特別障害者手当など)
- 税金の控除(住民税・所得税の障害者控除など)
- 生活の支援(おむつの支給、住宅改善資金助成など)
上記の内容のほかにも、各自治体が独自に実施する支援制度があるので、お住まいの地域で受けられる補助をあらかじめ調べておきましょう。
パーキンソン病を患っていても問題なく特養に入居できる!

今回は、パーキンソン病の方が特養に入居する際の条件をお伝えしました。
特定疾病に指定されているパーキンソン病では、要介護度3以上であれば、40歳を超えた時点で特養に入居できます。
現地に足を運び実際に施設を見て、ご本人とご家族の双方が納得できる特養を選びましょう。
本記事では特養に焦点をあててお伝えしましたが、パーキンソン病の方が快適に過ごせる施設は、なにもこれだけではありません。
有料老人ホームのスーパー・コートなら、パーキンソン病患者の介護に特化した「専門住宅」で、徹底的なサポートが可能です。
パーキンソン病の方が穏やかに暮らせる施設をお探しであれば、ぜひお問い合わせください。
監修者

花尾 奏一 (はなお そういち)
介護主任、講師
<資格>
介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
<略歴>
有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。











