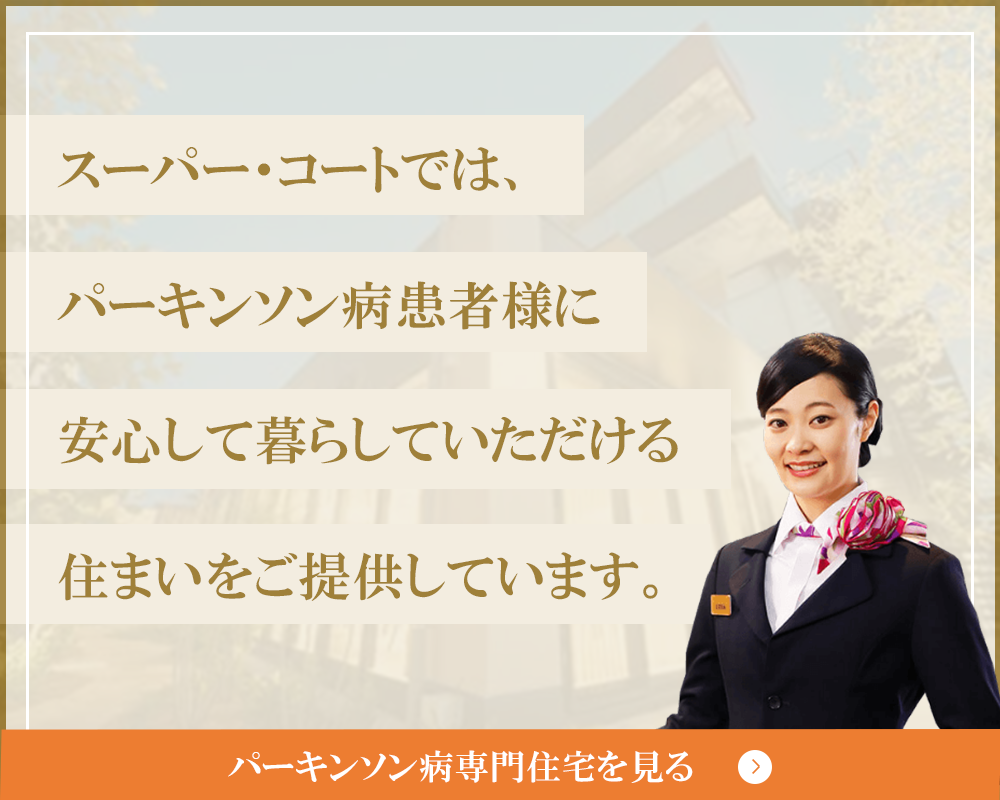column
コラム
公開日: 更新日:
パーキンソン病による睡眠障害と主な改善方法を紹介

不眠症や過眠症といった睡眠に関連した病気を、総じて「 睡眠障害」と言います。
睡眠障害は、パーキンソン病患者の方にもみられる症状の一つです。
パーキンソン病にかかると、具体的にどのような睡眠障害が起こるのでしょうか。
そこで本記事では、パーキンソン病による睡眠障害の症状とその改善方法をお伝えします。
パーキンソン病の治療を受けている方やご家族にとって、本記事でご紹介する内容が、少しでもお役に立てば幸いです。
パーキンソン病の主な症状とは
パーキンソン病は、身体の動きに障害が表れる全身疾患です。
中脳にあるドーパミン神経細胞が減少することで、生成されるドーパミンが不足し、発症するとされています。
ドーパミンとは、意欲や幸せを感じたり、学習・運動機能を調節したりするといった脳機能に関わる神経伝達物質のことです。
パーキンソン病の場合、ドーパミン神経細胞の不足により運動機能を調節するための脳の指令が筋肉にうまく伝わらなくなり、さまざまな運動症状が引き起こされます。
ドーパミン神経細胞以外にも、ノルアドレナリン神経細胞やセロトニン神経細胞なども変性するため、初期症状から進行期までに非運動症状が高頻度で併発します。
残念ながら、ドーパミン神経細胞が減少する明確な理由は分かっていません。
ただ現状では、遺伝や加齢が要因で、「αシヌクレイン」というタンパク質が神経細胞の中に凝縮・沈着することによって起こる異常だと考えられています。
パーキンソン病による運動症状と非運動症状とは、具体的にはどのような症状が起こるのでしょうか。
それぞれの症状の例をご紹介します。
運動症状
パーキンソン病の主な症状としては、身体の動きが不自由になる運動症状が挙げられます。
代表的な症状は、手足がふるえる「振戦」、 あらゆる動きが遅くなる「動作緩慢」、手足の筋肉がこわばる「筋強剛」、身体のバランスがとりにくくなる「姿勢保持障害」の4つです。
具体的には、以下の運動症状が日常生活でみられます。
【パーキンソン病による運動症状】
- 動きが小さくなったり遅くなったりする
- 歩行が小刻みになる
- 表情が乏しくなる
- 声が小さくなる
- 細かい動作ができなくなる
- 字が小さくなる
これらの症状は、左右差が生じることが多い傾向にあります。
また、運動症状では痛みを覚えることもあるため、五十肩だと思い治療を受けていたものの、しばらくして振戦が表れ、パーキンソン病と診断されることも少なくありません。
(参考:厚生労働省)
非運動症状
精神面をはじめとする非運動症状も、パーキンソン病にみられる症状です。
具体的には、以下のような症状が起こります。
【パーキンソン病による非運動症状】
- 睡眠障害
- 便秘
- 起立性低血圧
- 幻視
- 認知機能低下
- 意欲低下
- うつ症状
パーキンソン病の初期症状として多くみられる非運動症状を見分けられれば、運動症状が起こる前にパーキンソン病を早期発見することができます。
(参考:厚生労働省)
パーキンソン病にみられる睡眠障害とは

パーキンソン病による非運動症状のなかでも、睡眠障害にはさまざまな症状があります。
ここでは、4つの代表的な症状を紹介します。
不眠
精神的な緊張や不安によって引き起こされる不眠は、パーキンソン病の睡眠障害のなかでも代表的な症状です。
不眠は、一次性不眠症や精神生理学性不眠、神経症性不眠ともよばれています。
「今晩は眠らなくてはならない」と考えれば考えるほど眠れなくなることがあるように、毎晩眠れるかどうかを心配することが不眠の要因になります。
これは、眠ろうと意識することで神経が興奮して、中枢神経系に覚醒状態が起こり、かえって眠れなくなるという悪循環を繰り返すためです。
なお、不眠の治療方法には、運動療法をはじめとする生活指導や睡眠薬が用いられます。
(参考:厚生労働省)
レストレスレッグス症候群(RLS)
パーキンソン病の睡眠障害には、レストレスレッグス症候群(RLS)も含まれます。
レストレスレッグス症候群とは、就寝時に足に異常な感覚が生じ、足を動かさずにいられないという強い欲求が表れることを指します。
眠りにつくことを妨げられるその症状から、以前は「むずむず脚症候群」ともよばれていました。
これらの症状は夕方から夜間にかけて安静時に増悪し、身体を動かすことで軽快します。
原因としては、鉄欠乏によって、感覚制御に関連するドーパミン系の機能が低下することで生じると考えられており、ドーパミン作動薬で症状が改善する傾向にあります。
(参考:厚生労働省)
レム睡眠行動異常症(RBD)
睡眠時に見ている夢に合わせて手足が動いてしまうレム睡眠行動異常症(RBD)も、パーキンソン病による睡眠障害の一例です。
通常、夢を見ているレム睡眠のときは、筋緊張が低下して身体が緩んでいるため、手足は動きません。
ところが、レム睡眠行動異常症に罹患すると、筋緊張を抑制する神経のはたらきが低下して筋肉が緩まず、夢を見ていても身体が動かせる状態になります。
怖い夢を見ている場合だと、大声を上げるだけでなく、ときには手足を動かしたり、起き上がったりすることで怪我を負う可能性もあるため注意が必要です。
筑波大学 神経内科の発表データによると、レム睡眠行動障害の発症から10年以内にパーキンソン病を発症する確率は、50%だと分かっています。
レム睡眠行動異常症を発症する主な要因は、過度なアルコール摂取、疲労、不規則な生活習慣など、身体に負担がかかる行為です。
日頃から心身に負担をかけ過ぎていないかを見直したうえで、ストレスを溜めないことや生活習慣を整えることを心がけましょう。
(参照元:筑波大学 神経内科)
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群も、パーキンソン病の睡眠障害によって引き起こされる症状です。
公益社団法人 日本生体医工学会の発表によると、パーキンソン病患者の半数近くは、睡眠中に無呼吸・低呼吸状態となる睡眠時無呼吸症候群を併発することが分かっています。
睡眠中に何度も息が止まると眠りの質が悪くなり、血液中の酸素が欠乏します。
これにより、心臓、脳、血管に負担がかかり、脳卒中や心筋梗塞などの合併症を起こす危険性もあるわけです。
しかし、睡眠中に呼吸が止まっているかどうかをご自身で判断することは容易ではありません。
睡眠時無呼吸症候群にはいくつかの特徴があるため、該当するものがないかお確かめください。
【睡眠時無呼吸症候群の特徴】
- 周りからいびきを指摘される
- 夜間の睡眠時によく目が覚める
- 起床時に頭痛や身体のだるさがある
- 日中に眠気がある
睡眠時無呼吸症候群は、治療によって症状が劇的に改善しますので、日常生活においてこれらの症状に身に覚えがある場合には、早めに医師に相談しましょう。
(参考:公益社団法人 日本生体医工学会)
関連記事:パーキンソン病の発症後に幻覚症状が現れる理由と治療・対処方法
パーキンソン病の睡眠障害を改善する方法

パーキンソン病による睡眠障害は、日中の過ごし方が要因になっている場合があります。
睡眠障害を改善するために、生活習慣を見直すうえで押さえておきたい、3つのポイントをご紹介します。
ポイント①日中に活動する
リハビリテーションや趣味などの活動を日中に活発的に実施し、身体を動かすことによって、睡眠障害を改善することができます。
昼間の活動量を増やすことで身体が疲労感を覚えれば、規則正しい生活リズムを取り戻せるので、夜は自然と眠くなります。
起床したら朝日を浴びて覚醒を促すことも、睡眠と覚醒のリズムを調整するのに有効な手段です。
また、日中に眠っている時間が長いと、夜間に眠れなくなるため、昼寝は午後3時前までに1日1回、30分以内に留めるのが理想的です。
ポイント②夕食以降の水分摂取を控える
夕食以降に飲む水の量を調整することも、睡眠の質を高めることにつながります。
寝る前に水分を摂りすぎて夜間に尿意を感じると、睡眠が妨げられ、トイレに行ったあとに眠れなくなることがあります。
日中の活動時には、しっかりと水分を補給して、夕食以降はできるだけ控えましょう。
ポイント③睡眠の質を高める工夫を施す
ストレスを感じずに熟睡するためには、睡眠の質を高める工夫を凝らすことも大切です。
基本的に寝室は、ゆったりと心安らぐ気分を感じられるように整えてみてください。
落ち着いた暖色系の寝具・カーテン、明度の低いやわらかな電球色の照明、アロマオイルなどを用いれば、お気に入りのくつろぎ空間を演出できます。
くわえて、お風呂の湯加減は熱すぎないように設定し、就寝する1~2時間前を目安に入りましょう。
また、就寝前にパソコンやスマートフォンの閲覧、お酒、たばこ、コーヒーなどを控えることも、深い眠りを促すためのコツです。
関連記事:パーキンソン病にみられる4大症状と初期・中期・末期症状の特徴
施設選びや介護にお悩みのかたはお気軽にご相談ください。
介護相談のプロがあなたのお悩みに寄り添い、最適な施設をご紹介いたします。
パーキンソン病による睡眠障害は、日中の活動や夜間の水分摂取量を意識することで改善につながる
今回は、パーキンソン病の睡眠障害とその改善方法をお伝えしました。
パーキンソン病による主な睡眠障害は、不眠、レストレスレッグス症候群、レム睡眠行動異常症、睡眠時無呼吸症候群です。
睡眠障害を改善するには、日中に十分に活動することを心がけたうえで、夕食以降の水分摂取量を控えたり、睡眠の質を高める工夫を施したりしましょう。
有料老人ホームスーパー・コートでは、建物の設計や介護の体制など、パーキンソン病患者の方に特化したパーキンソン病専門住宅をはじめとする56施設を展開しています。
専門の病院で知識・技術を深めた理学療法士や作業療法士が、良質なリハビリテーションを提供いたしますのでぜひ一度ご相談ください。
監修者

花尾 奏一 (はなお そういち)
介護主任、講師
<資格>
介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
<略歴>
有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。