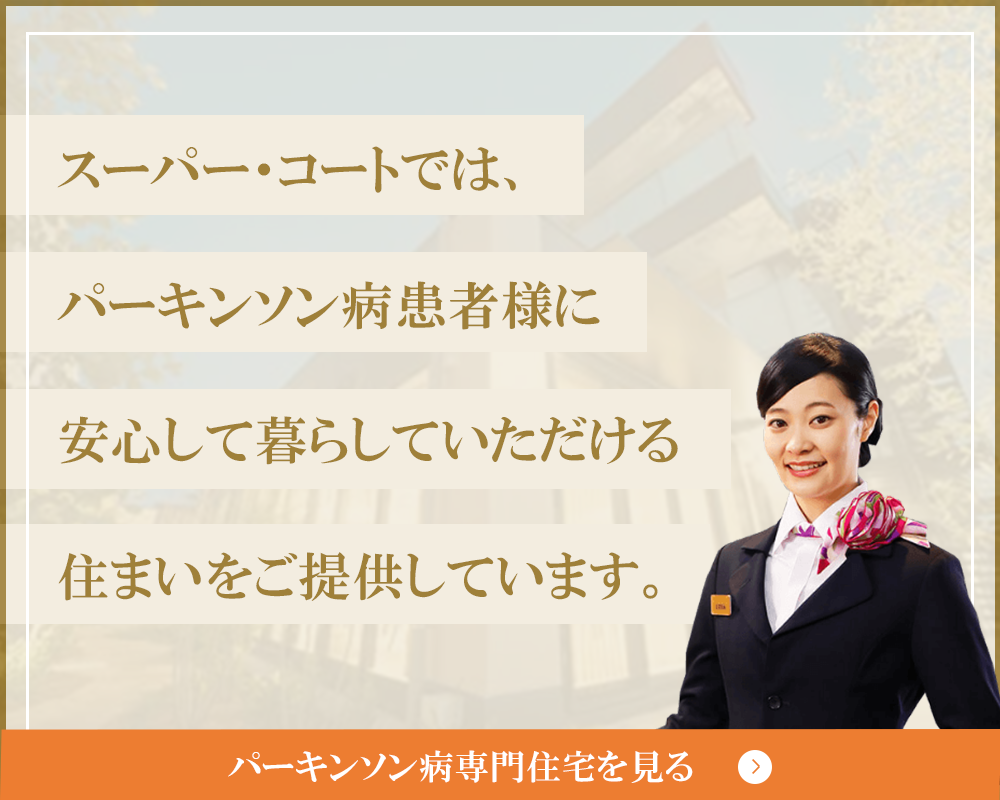column
コラム
公開日: 更新日:
パーキンソン病は予防できる?主要な症状もあわせて解説

パーキンソン病は、国から指定難病の認定を受けている病気の一つです。
現在の医療において根本的な治療法は確立されていないため、できる限り発症したくないものです。
しかし、パーキンソン病は予防することができるのでしょうか?
本記事では、パーキンソン病の症状を解説したのち、予防できるのか否かをお伝えします。
将来の不安を取り除き、明るい未来を描けるよう、ぜひ最後までご覧ください。
パーキンソン病の概要
まずは、パーキンソン病の概要を確認していきましょう。
主に身体の動きに障害が表れる病気を、パーキンソン病といいます。
中脳の黒質とよばれる部分にあるドーパミン神経細胞が減少し、ドーパミンの生成量が減ることで引き起こされます。
ドーパミンとは、意欲や幸福感をもたらすほか、運動機能を調節するといった脳機能に関わる神経伝達物質のことです。
ドーパミンが不足してパーキンソン病を発症すると、身体の動きをコントロールする脳からの指令が筋肉に伝わらなくなり、さまざまな症状が表れます。
残念ながら、医療が発展している現在においても、ドーパミン神経細胞が減少する原因はいまだに判明していません。
ただし、遺伝や加齢によって、αシヌクレインというタンパク質が神経細胞のなかに凝集・沈着することが原因ではないか、というのが通説として考えられています。
パーキンソン病の主要な症状

先ほど、パーキンソン病を発症すると、主に身体の動きに障害が表れると説明しましたが、それ以外の面でも症状がみられる場合があります。
ここからは、パーキンソン病の主要な症状を、運動症状と非運動症状に分けて紹介していきます。
運動症状
まずは、パーキンソン病の運動症状を確認していきましょう。
身体のふるえ
パーキンソン病の症状のなかでも、初期からみられるのが身体のふるえです。
特に、安静にしている状態の手足でみられる傾向にあります。
初めのうちは、左右どちらかにのみ症状が表れますが、進行すると両方の手足でみられるようになります。
身体のこわばり
身体のこわばりも、パーキンソン病が原因で起こる症状の一つです。
パーキンソン病を発症すると、筋肉の収縮と弛緩のバランスが崩れて、筋肉の緊張が進むため、四肢の関節が硬くなってしまいます。
これによって、手足の動きがぎこちなくなったり、歩くときに腕を振らなくなったりといった症状が表れます。
寡動(動作が遅くなる)
一つひとつの動作が遅くなる「寡動」も、パーキンソン病の方を悩ます症状として挙げられます。
この症状が表れると、動き始めるのに時間がかかるうえ、動作自体が遅くなってしまいます。
それと付随して、自発的な行動が減少するため、次第に筋力が低下し、ますますじっとしている時間が増えるという悪循環に陥ることも少なくありません。
姿勢反射(転びやすくなる)
パーキンソン病の症状には、姿勢反射もあります。
姿勢反射とは、身体のバランスをうまく保てず、転びやすくなってしまう症状のことです。
特に、以下のような歩行障害がみられます。
姿勢反射の症状によってみられる歩行障害
| 名称 | 特徴 |
| すくみ足 | 最初の一歩が出づらく、歩行の流れが止まる |
| 小刻み歩行 | 前傾姿勢で、歩幅は小刻みになり、腕の振り幅も狭くなる |
| 突進歩行 | 一度歩き始めると、どんどん加速してしまい、自分では止まれない |
こうした歩行障害が起きると、転びやすく危険なため、他者の見守りが必要になります。
非運動症状
では、パーキンソン病の非運動症状には、どのようなものがあるのでしょうか。
精神症状
パーキンソン病の非運動的な症状の一つには、精神症状が挙げられます。
具体的には、抑うつやパニック発作、幻視、妄想といった症状です。
これらの精神症状は、パーキンソン病によるものだけでなく、治療薬の副作用として引き起こされている場合もあります。
自律神経障害
自律神経障害も、パーキンソン病でみられる非運動的な症状の一つです。
パーキンソン病を発症すると、自律神経の乱れを引き起こす可能性があります。
自律神経は、外部からの刺激に対して無意識に身体の機能をコントロールする役割を担う神経です。
私たちが生きていくうえでは欠かせない神経ですので、自律神経が乱れてしまうと便秘や排尿障害、発汗異常といった症状が表れます。
認知機能障害
パーキンソン病では、集中力や注意力の低下など、認知症とよく似た症状がみられる場合もあります。
ただし、認知症でみられるような、記憶障害は目立って表れないため、気づきにくいのが特徴です。
睡眠障害
パーキンソン病の症状として最後に紹介するのが、睡眠障害です。
パーキンソン病は、心身に安らぎをもたらし、精神を安定させる「セロトニン」という神経伝達物質にも影響を与えます。
これによって、深い眠りにつけない、睡眠中に異常行動をとるなどの症状がみられます。
関連記事:パーキンソン病の発症原因とは?初期症状や似ている病気もチェック
パーキンソン病の予防方法
パーキンソン病には、さまざまな症状があり、日常生活に多くの影響を与えることがわかりました。
それでは、パーキンソン病を予防することはできるのでしょうか?
結論から言うと、パーキンソン病を発症する原因が解明されていないため、確実に予防できる方法は、現状存在しません。
しかし、パーキンソン病の予防につながると考えられている行動はいくつかあります。
その例を以下にまとめました。
【パーキンソン病の予防方法】
- 食生活を見直す
- カフェインが含まれる飲料を飲む
- 運動習慣を身につける
- ドーパミンが増える行動をとる
それでは順に、確認していきましょう。
食生活を見直す
食生活を見直すことで、パーキンソン病を発症するリスクを減らせると考えられています。
一般的に、以下のような食べ物は、発症のリスクを高める可能性がありますので、避けるのが望ましいです。
【パーキンソン病のリスクを高めるおそれがある食べ物の特徴】
- しょ糖を多く含んでいる
- 動物性脂肪を過度に含んでいる
- 農薬が付着している
武庫川女子大学の研究では、パーキンソン病の方はそうでない方に比べて、しょ糖を含む菓子類の摂取量が多い傾向にあることが明らかになっています。
また、愛媛大学医学部の研究によって、動物性脂肪に含まれるコレステロールの摂取量が多いほど、パーキンソン病のリスクが上がることが判明しました。
農薬についても、パーキンソン病のリスクを上げることが示唆されており、フランスでは、農業従事者の職業病として認定されています。
こうした理由により、しょ糖や動物性脂肪を多く含んだ食べ物は避け、野菜のように農薬が付着している可能性がある食べ物は、きちんと洗浄してから食べるのがポイントです。
(参照:武庫川女子大学|パーキンソン病患者における食事内容と病態との関連に関する研究)
(参照:愛媛大学|脂肪酸摂取とパーキンソン病リスクとの関連)
(参照:環境脳神経科学センター|パーキンソン病と農薬)
カフェインが含まれる飲料を飲む
カフェインが含まれる飲料を飲むことも、パーキンソン病の予防につながると考えられています。
シンガポールの研究機関によると、コーヒーや紅茶を飲む方は、全く飲まない方に比べて4~8倍もパーキンソン病を発症しにくい傾向にあることが判明しました。
カフェイン飲料を飲むだけなので、簡単にパーキンソン病の予防ができますよ。
しかし、カフェインの摂りすぎは、かえって健康被害をもたらすリスクもあるので、飲みすぎには注意が必要です。
目安として、コーヒーであれば1日に3杯を限度に飲みましょう。
(参照:The Lancet Regional Health – Western Pacific)
運動習慣を身につける
パーキンソン病のリスクを予防するには、運動も欠かせません。
というのも運動には、筋力の低下を防ぎ、ドーパミンの分泌を増やす効果があるとされているからです。
水泳やテニスなどの本格的なスポーツもよいですが、運動初心者の方には、ラジオ体操や散歩をおすすめします。
どちらも費用がかかりませんし、身体に過度な負荷をかける心配もありません。
パーキンソン病を予防したいのであれば、無理せず継続的に取り組むことが大切です。
健やかな身体で日々を過ごすためにも、運動の習慣化を目指してみてください。
ドーパミンが増える行動をとる
パーキンソン病の原因でもある、ドーパミンの不足を防ぐためにも、ドーパミンが増える行動を日常的にとりましょう。
ドーパミンを増やす方法としては、「好きなことや得意なことに取り組む」「チロシンが含まれる食品を食べる」の2つが挙げられます。
意欲や幸福感をもたらすドーパミンは、ご自身が好きなことや得意なことをすると分泌量が増えると考えられています。
趣味のように夢中になれることを全力で楽しみ、たくさん笑う機会が増えると、なお効果的です。
また、チロシンが豊富に含まれるアーモンドや大豆、かつお節などの食べ物を、日常的に摂取するように心がけてください。
タンパク質の一種であるチロシンは、ドーパミンをはじめとする神経伝達物質の原料になる栄養素です。
チロシンが含まれた食べ物を食べることで、ドーパミンの生成を助ける効果が期待できます。
関連記事:パーキンソン病にいい食べ物と摂りすぎに気をつけたい食べ物
パーキンソン病の症状が出たらどうする?

これまで紹介した予防方法を講じていたとしても、パーキンソン病を発症することはあります。
もしパーキンソン病になったら、すみやかに医療機関を受診しましょう。
早期に治療を開始すれば、そのぶん症状の進行を緩やかにできるかもしれません。
以下では、パーキンソン病の症状が出た際の行動や治療法を解説していきます。
検査を受ける
パーキンソン病の症状が表れたら、まずは医療機関で検査を受けましょう。
検査の内容は、主に問診と手足の動作を確認する神経学的検査、CTやMRIを用いた画像検査の3つです。
検査の結果、以下が確認されるとパーキンソン病の診断を受けます。
【パーキンソン病の診断を受ける4つの要件】
- 代表的な4つの身体の運動に関する症状がみられる
- 脳血管障害や脳変性疾患ではないことが証明される
- CTやMRI検査で脳には異常がないことが判明する
- 症状の原因が薬によるものではないことが確認される
上記の4つが確認されたら、パーキンソン病の症状を緩和するために、リハビリや薬物療法、手術を受けることになります。
リハビリに取り組む
パーキンソン病を発症しても、できる限り長く元気に過ごすためには、リハビリに取り組むことが大切です。
パーキンソン病になるとスムーズに身体が動かせなくなるため、思い通りに活動するのが難しくなるものです。
だからといって活動を控えてしまうと、身体の機能がより低下するので、日常的にリハビリに取り組むことが求められます。
パーキンソン病の方が取り組むリハビリには、以下のようなものがあります。
パーキンソン病の方が取り組むリハビリの種類
| 項目 | リハビリの目的 |
| リラクゼーション | 肉体的・精神的な緊張をほぐしてリラックスさせる |
| ストレッチ・柔軟体操 | 身体の柔軟性を高め、筋肉を伸ばす |
| 生活動作練習 | 着替えや食事、排せつなど、支障の出ている場面に合わせた練習を行い、生活動作を改善する |
| 筋力強化運動 | 弱ってしまった部分の筋力を強化する |
| 構音練習 | 声の小ささや抑揚の乏しさを改善する |
| 嚥下練習 | 食べ物をうまく飲み込めるようにする |
こうしたリハビリに取り組むうえで意識したいのは、症状の進行度に合わせて内容を調整することです。
進行度にきちんと寄り添えていれば、効果的なリハビリが実施でき、症状の緩和が期待できます。
ですから、パーキンソン病を発症した際は、理学療法士や作業療法士などの指導のもと、ご自身の身体の状態に合わせたリハビリに取り組むようにしましょう。
薬を服用する
現在実施されているパーキンソン病の治療法として代表的なのは、薬物療法です。
薬物療法では、ドーパミンの補充や代替、または分解の阻害や分泌の促進のいずれかの効果をもつ薬が用いられます。
服用する薬の種類や量、組み合わせなどは、患者さまの状況によって異なります。
いずれの薬も、副作用が出る可能性があるため、医師にあらかじめ確認し、患者さま本人と
| 病名 | 概要 |
| 薬剤性パーキンソン症候群 | 一部の精神安定剤や胃薬の副作用でドーパミンのはたらきが抑えられ、パーキンソン病と似た症状が引き起こされる |
| 慢性硬膜下血腫 |
|
| 正常圧水頭症 |
|
| 脳血管性パーキンソン症候群 |
|
| レビー小体型認知症 |
|
| 進行性核上性麻痺 |
|
| 多系統萎縮症 |
|
ご家族がリスクを十分に納得したうえで服用するのが望ましいです。
脳の手術を受ける
「薬物療法では、パーキンソン病の症状をうまくコントロールできない」と医師に判断された場合に限りますが、脳の手術が必要になることもあります。
パーキンソン病における脳の手術は、脳深部刺激療法と凝固術(MRガイド下集束超音波(FUS))の2種類に分けられます。
脳深部刺激療法
脳深部刺激療法は、脳の深部に電極を設置し、胸に刺激を送る電池装置を埋め込む手術です。
これによって、脳深部で過剰に活動している神経核に刺激を与え、その活動を抑制することができます。
症状の緩和にくわえて、薬の副作用を軽減する効果も期待されています。
凝固術(MRガイド下集束超音波(FUS))
脳深部刺激療法による手術が受けられず、そのうえ身体のふるえがよく表れている場合は、凝固術(MRガイド下集束超音波(FUS))が行われます。
凝固術は、脳内の特定の部位に熱を加える手術法です。
手足のふるえを緩和し、1日における症状の変化を落ち着かせる効果が期待できます。
ただし、手術の効果には個人差があるほか、持続的な効果が得られない可能性もあります。
パーキンソン病と似た症状を引き起こす病気
ここまでご紹介してきたのは、症状が表れて実際にパーキンソン病だったケースでしたが、じつは似た症状をもつ別の病気だった、というケースもあります。
こうした病気を総称して、「パーキンソン症候群(パーキンソニズム)」といいます。
パーキンソン症候群のなかには、どのような病気があるのでしょうか。
パーキンソン症候群の一覧
以上の7つが、パーキンソン症候群とよばれています。
これらの病気だった場合は、パーキンソン病の治療薬で効果を得るのは難しく、治療法も異なるため、正しく診断を受けることが欠かせません。
したがって、パーキンソン病と診断されても、ほかの病気の疑いがあるのであれば、セカンドオピニオンを受けることも視野に入れましょう。
パーキンソン病の方の介護でお悩みならスーパー・コートにお問い合わせを
「パーキンソン病に苦しむ本人のために、何をすべきかわからない」「どうしたら快適に過ごせるだろう……」と、お悩みのご家族さまもいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような悩みを解決できるのが、パーキンソン病の患者さまに特化した専門住宅を提供する、有料老人ホームスーパー・コートです。
有料老人ホームスーパー・コートの専門住宅は、建物の設計から介護の体制、提供するサービスに至るまで、パーキンソン病のご入居者さまの介護に特化しています。
看護師が24時間常駐しており、ご入居者さまの小さな体調の変化にも即座に気がつき、対応することが可能です。
また、専門の病院で知識や技術を深めた理学療法士や作業療法士によって、一人ひとりの状態に合ったリハビリを提供しております。
このように、パーキンソン病の方が安心して過ごしていただける環境が整っておりますので、まずはお問い合わせください。
施設選びや介護にお悩みのかたはお気軽にご相談ください。
介護相談のプロがあなたのお悩みに寄り添い、最適な施設をご紹介いたします。
パーキンソン病に確実な予防方法はないが、食事の見直しや運動習慣の構築を行うとよい
本記事では、パーキンソン病の症状とともに、予防できるのか否かを解説しました。
パーキンソン病は、主に身体の動きに障害が表れる病気です。
発症の原因が解明していないため、確実な予防方法は存在しませんが、食生活の見直しや運動習慣の構築などが予防につながると考えられています。
パーキンソン病の発症リスクを下げたいのであれば、これらを無理のない範囲で取り入れ、健康的な生活を送ることを意識しましょう。
有料老人ホームスーパー・コートでは、パーキンソン病の方に特化した専門住宅を提供しております。
入居者さまの「自分らしく生きたい」という想いを全力で叶える環境が整っておりますので、もしものときは、ぜひご利用ください。
監修者

花尾 奏一 (はなお そういち)
介護主任、講師
<資格>
介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
<略歴>
有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。