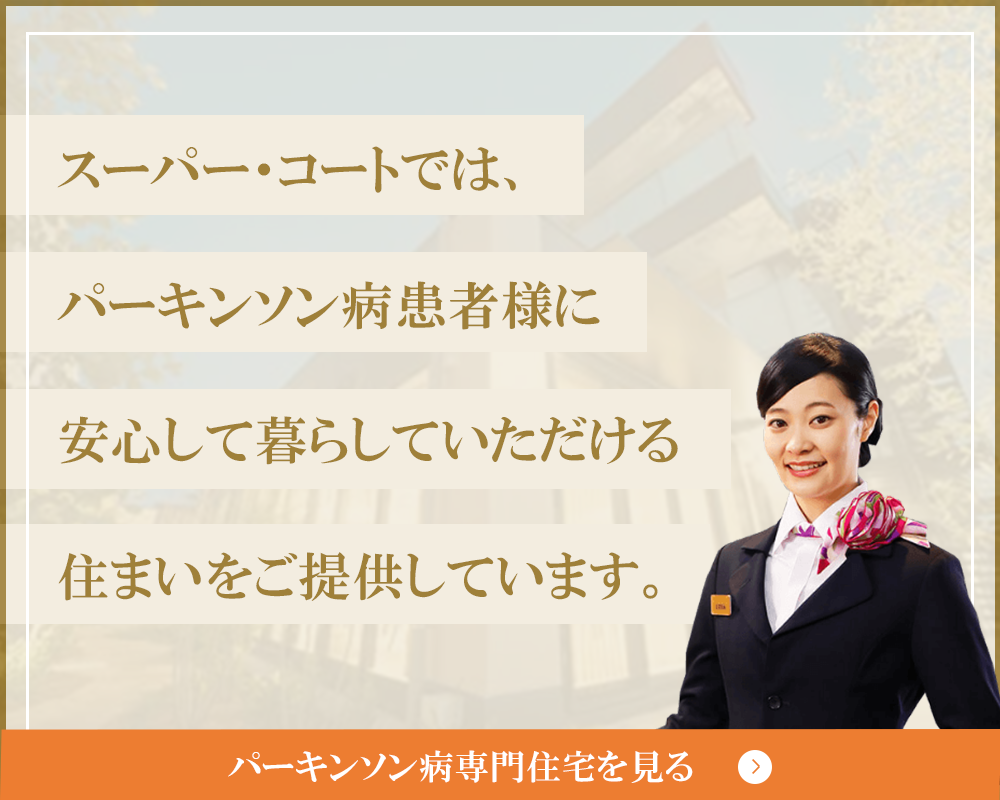column
コラム
公開日: 更新日:
パーキンソン病の発症後に幻覚症状が現れる理由と治療・対処方法

パーキンソン病は、脳内で分泌される神経伝達物質・ドーパミンの量が減っていくことで、運動機能やその他の機能が低下する病気です。
外見的には手足の震えや筋肉が固まる症状といった運動機能の低下が確認できますが、精神症状として幻覚やうつ症状が現れることがあります。
この記事では、パーキンソン病によって出現する可能性のある精神症状について紹介します。
幻覚症状について詳しく取り上げ、幻覚症状を抑える治療法や対処法も解説していますので、ぜひ参考にしてください。
パーキンソン病の精神症状
パーキンソン病の精神症状にはいくつかの種類があります。
幻覚・妄想・うつ症状・ドーパミン調節異常症候群の代表的な4種類についてみていきましょう。
症状①幻覚
幻覚は、実在しないもの・景色・状況を経験する、または実在しないものや景色を見たと信じる症状です。
パーキンソン病の非運動症状(筋肉の動きに関係しない症状)であり、精神症状として区別されています。
パーキンソン病の治療中は症状の進行とともにこの幻覚が現れる場合がありますが、治療薬の副作用が原因で幻覚を起こすこともあります。
症状②妄想
妄想は、誤った思い込みや誤解を信じ込むことです。
パーキンソン病に罹患した約半数の方に、非運動症状として妄想が現れることもあります。
実際には存在しないことを強く信じ込み、日常生活に支障をきたす方もいます。
妄想も幻覚と同じように、治療薬の副作用が原因で引き起こす場合があります。
妄想の症状に対してとられる方法としては、抗パーキンソン病薬の変更や減量または中止を行い、最後に追加した薬から減らしていきます。(※)
※参考元:公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センター「パーキンソン病(指定難病6)」
症状③うつ症状
うつ症状は、将来の不安や気分の落ち込み、意欲の低下など、精神的な状態に影響を与える症状です。
パーキンソン病の患者さんは筋力の低下によって日常生活にさまざまな支障をきたし、「アンヘドニア」と呼ばれる、体の五感に関連した喜びが減少しやすい傾向にあることから、アンヘドニアとうつ症状の関連性が示唆されています。(※)
精神科での治療が必要なうつ病とは異なるともいわれていますが、気分の落ち込みには個人差があるため、うつ症状が認められる場合は薬の減量や変更によって様子をみます。
※参考元:精神神経学雑誌オンラインジャーナル「パーキンソン病と抑うつ」
症状④ドーパミン調節異常症候群
ドーパミン調節異常症候群(DDS)は、長期間にわたってドーパミン補充療法を受けたときに、報酬系と呼ばれる機能がなんらかの異常をきたし、異常行動を引き起こす症状です。
報酬系とは、脳内にある神経系の呼び名です。
神経伝達物質であるドーパミンが分泌されると、この報酬系が活性化し、満足感や達成感を得られます。
しかし、ドーパミン補充療法によって報酬系に異常が発生すると、次のような行動をとることがあります。(※)
【ドーパミン調節異常症候群による行動】
- 薬の過剰服用
- 金銭の浪費
- 性的逸脱
- インターネット依存
- 趣味への没頭
- 徘徊ないし目標のない散歩
ドーパミン調節異常症候群では衝動的な行動から中長期的な依存まで、さまざまな症状がみられます。
薬の副作用が疑われる場合は、専門医に相談し、薬の減量や変更を行います。
※参考元:J-Stage「Parkinson病患者の行動障害*」
パーキンソン病を発症すると幻覚の症状が現れるのはなぜ?

パーキンソン病によってなぜ幻覚が現れるのかは、はっきりと解明されていません。
脳内の化学物質とその受容体が関連していると考えられ、2つの原因に分けることができます。
【パーキンソン病による幻覚の原因】
- パーキンソン病の自然な経過
- ドーパミン作動薬による副作用
パーキンソン病の症状が進んでくると、ドーパミン神経が減少したりその他の神経もダメージを受けたりして、神経系の変化がきっかけとなり、自然な経過として症状が現れてきます。
ドーパミン作動薬は、パーキンソン病の治療薬のことです。
脳内のドーパミン値を上昇させて治療を施すものですが、副作用として幻覚が現れてくるケースがあります。
幻覚が明らかに薬の影響である場合は、用量を減らすか他の薬に変更して対応しなければなりません。
はじめのうちはパーキンソン病の自然な経過によるものなのか、薬の副作用なのかすぐに判断がつかないため、脳血流シンチグラフィーやその他の検査を行い、総合的に診断します。
パーキンソン病による幻覚症状に対する家庭での対応方法
パーキンソン病の患者さんに幻覚症状が現れるときは、どのように対応すればよいのでしょうか。代表的な3つの方法をみていきましょう。
対応方法①生活環境を整える
幻覚を防ぐためには、まず幻覚が起こりにくい環境を整えることが大切です。
一例として、パーキンソン病の症状が進行すると記憶力が低下することがあります。
いつも財布をしまっておく場所に財布がないと、「誰かに盗まれたかもしれない」とネガティブな想像をしてしまい、そこから幻覚が現れるおそれがあります。
幻覚が起こりにくくなるように、部屋を散らかさないようにする・貴重品は定位置に置いておく(忘れやすい場合は目印や紛失防止タグを活用する)といった工夫が求められます。
対応方法②否定せずに受け入れる
患者さんと同居しているご家族は、いきなり幻覚の症状について訴えられると戸惑ってしまうかもしれませんが、感情的や否定的な対応はかえって幻覚を増長させるおそれがあります。
「大丈夫」「何もしないよ」などと、患者さん自身の恐怖心を取り除くような声かけや、やさしい対応を心がけたいところです。
対応方法③体調管理を行う
いままでにない症状が出たりしたときは専門医に相談し、パーキンソン病治療薬が合わない可能性があると示された場合は、治療薬を減らしたり変えたりする必要があります。
具合が悪いときに無理な外出や運動は避け、自分自身を追い込むようなストレスの原因からも、できるかぎり遠ざかるように工夫することが大切です。
パーキンソン病による幻覚症状を抑える治療法
パーキンソン病による幻覚症状を抑える治療法は次のとおりです。
【パーキンソン病の幻覚を抑える治療法】
- 抗パーキンソン病薬の変更
- 抗パーキンソン病薬の減量
- 抗認知症薬の使用
- 向精神薬の使用
- 漢方薬の使用
幻覚以外の症状がどの程度進行しているかにもよりますが、医師に相談のもと、服用中の薬の変更や減量を行って様子を見ます。
症状に合わせて抗認知症薬や向精神薬を組み合わせたり、漢方薬のように強い副作用の心配が少ない薬を取り入れたりするケースもあります。
関連記事:パーキンソン病は治る?治療の効果、新しい治療と注意したいポイント
パーキンソン病の幻覚症状の治療前に確認すべきこと
パーキンソン病の幻覚症状の治療を始める前に確認しておくべきポイントを紹介します。
ポイント①周囲の危険から遠ざける
周囲に幻覚を引き起こすストレス源がある場合は、それらの危険から患者さんを遠ざけます。
患者さん自身が拒否反応を示しているものがあるときは、そこに近づかないようにするだけでも興奮のリスクを抑えられます。
鋭利なものや熱いもの、凶器になりうるような危険物が近くにあるときは近づかないように誘導し、患者さんを落ち着かせます。
ポイント②幻覚の原因を理解する
幻覚は脳が何らかの異常を示しており、患者さん自身も辛いと感じている状態です。
まずは幻覚を引き起こしている原因がどこにあるのかを把握し、介護者や医師、看護師もよく理解する必要があります。原因が特定できれば、その原因を取り除いて症状を改善できる可能性があります。
ポイント③話を合わせる
幻覚を見ている患者さんと話を合わせて、幻覚のとおりに対応することも有効な対処法のひとつです。
「虫がいる」と言われたときに、「虫なんていない」と否定をするのではなく、「じゃあ取ってみるね」と話を合わせるようにします。
患者さんを別の場所に待機させて、「虫を外に出したからもう大丈夫だよ」と言って安心させると、恐怖心や興奮状態が抑えられます。
関連記事:パーキンソン病は治る?治療の効果、新しい治療と注意したいポイント
施設選びや介護にお悩みのかたはお気軽にご相談ください。
介護相談のプロがあなたのお悩みに寄り添い、最適な施設をご紹介いたします。
幻覚はパーキンソン病の非運動症状の一種

今回は、パーキンソン病によって現れる精神症状と幻覚症状の対処法について紹介しました。
幻覚は非運動症状の一種で、薬の副作用や病気の進行によって引き起こされることがあり、適切な治療や環境の整備が必要です。
慣れないうちは、幻覚を直接否定せず、患者さんの気持ちに立って対応するようにしましょう。
スーパー・コートではパーキンソン病専門住宅を運営しており、パーキンソン病のご入居者の運動機能の維持や生活の質の向上を目指した取り組みにも力を入れているので、ぜひご相談ください。
監修者

花尾 奏一 (はなお そういち)
介護主任、講師
<資格>
介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
<略歴>
有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。