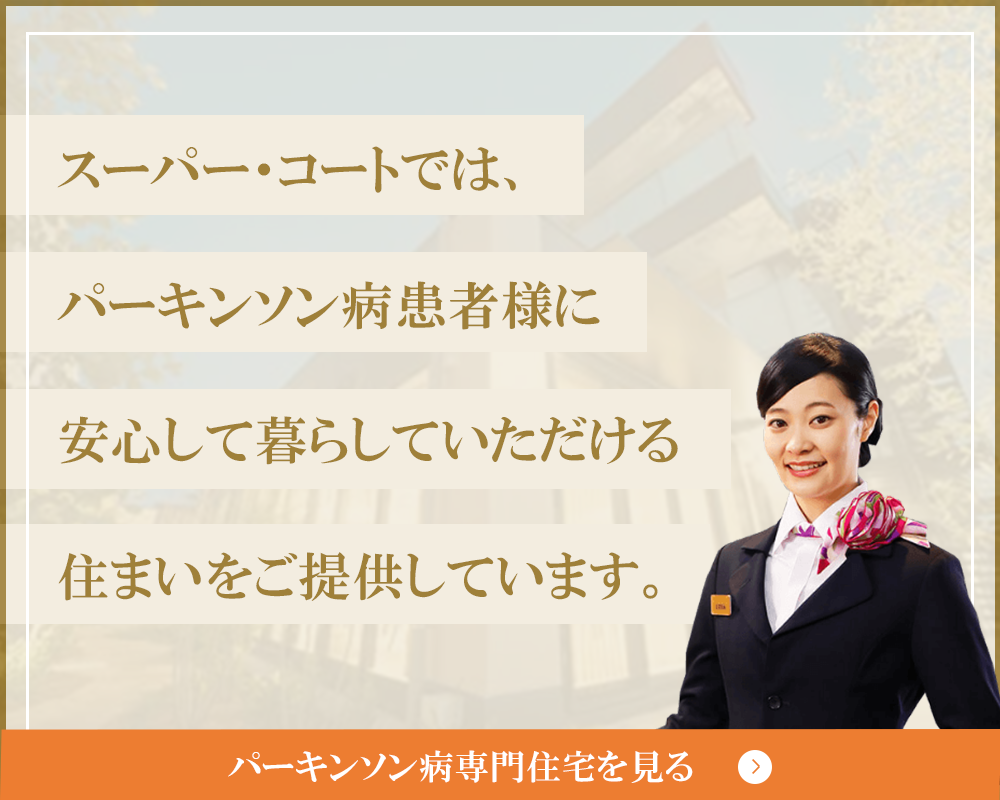column
コラム
公開日: 更新日:
パーキンソン病の原因になりやすい食事と予防に効果が期待できる食材

パーキンソン病は、脳内でドーパミンの分泌量が減ってしまい、筋肉の機能低下が起きる病気です。
遺伝や加齢などさまざまな原因が考えられていますが、偏った食事も発病リスクを高めるのではないかといわれています。栄養バランスが乱れた食生活は生活習慣病の原因にもなるため、毎日の食事を見直すことが大切です。
ここでは、パーキンソン病の発症と食事の関係について紹介しています。
注意したい食事内容や予防のためにできる心がけも取り上げていますので、ぜひ参考にしてください。
パーキンソン病の発症には食事が関係している?
パーキンソン病は、中脳にあるドーパミン神経細胞が減少することで、生成されるドーパミンが不足し発症する病気です。
偏った食事によって必ず発症するというわけではなく、食事との因果関係についてははっきりとわかっていません。
ただし、偏りすぎた食事は脳にも悪影響のおそれがあり、食生活の乱れによって病気に影響が出る可能性も一部では指摘されています。
パーキンソン病の原因となりうる食事

パーキンソン病に悪影響となる要素は、次の5つです。
【パーキンソン病の原因になりうる食事の要素】
- 動物性脂肪
- 過剰な糖分
- 低脂肪乳製品
- 残留農薬
- アルミニウム
それぞれの要素が、どのようにパーキンソン病に影響を与えるのかについて確認していきましょう。
原因要素①動物性脂肪が多く含まれる食事
肥満や生活習慣病の直接の原因になる動物性脂肪は、バターやラード、脂肪分の多い乳製品などが挙げられます。
動物性脂肪の多い食材を使ったメニューを日常的に摂取していると、ドーパミンの減少につながる可能性があります。
動物性脂肪も栄養の一種であり、体のバランスを整えるために必要ですが、たくさん摂りすぎると健康には良くありません。
バランスのとれた食事内容を意識し、脂肪分を減らす工夫が大切です。
原因要素②過剰な糖分を摂取する食事
砂糖に代表される糖分は、過剰に摂取することでパーキンソン病の発症リスクが上がる可能性があります。
糖と脂質が体内で結合し、「糖脂質」となったときに、パーキンソン病の発症リスクが高まるという研究もされているため、甘いものや炭水化物を摂りすぎないようにしましょう。
炭水化物はエネルギー源として利用されるため、極端な糖質制限は望ましくありません。
一方で、炭水化物の食事と一緒に甘いデザートや飲みものを摂ると、発症リスクが上がる可能性に注意しなければなりません。
原因要素③低脂肪乳製品を含む食事
動物性脂肪が含まれる食事はパーキンソン病の発症リスクを高める可能性がありますが、低脂肪乳製品 も同様にリスクを上げる可能性が指摘されています。
この研究結果は2017年にアメリカの研究グループが「Neurology」に発表したもので、低脂肪乳製品の摂取もパーキンソン病の発症リスクに関連していたことが判明しました。(※)
研究では一般的な乳製品と低脂肪乳製品の両方を調査し、どちらもパーキンソン病の発症リスクに関わるとしています。
※参考元:Neurology(2017; 89: 46-52)「Intake of dairy foods and risk of Parkinson disease」
原因要素④農薬が残った食材を用いた食事
農薬は神経系への障害作用があり、パーキンソン病の発症因子として多くの研究結果が報告されています。(※)
除草剤や殺虫剤などの農薬は、使用法が守られていれば多少残留していても健康被害が出ることはほとんどないとされています。
しかし、薬剤が付着したままの野菜や果物をそのまま口にしないよう、十分に注意が必要です。
調理前には、外側の葉をむいたり、洗ったり、皮をむいたり、下茹でをするなどの下処理を心がけましょう。
また、減農薬野菜や無農薬野菜を選ぶことも、一つの選択肢です。
※参考元:J-Stage「農薬による人体の慢性障害」
原因要素⑤アルミニウムを含む食事
アルミニウムは、ボーキサイト鉱石を原料とする重金属の名称です。
アルミニウムは土壌・水・空気中などの自然界にも存在し、食品添加物や医薬品にも含まれています。(※1)
自然界に存在するアルミニウムは微量ですが、添加物については低濃度のアルミニウムでも脳内では炎症の活性レベルが上がるとされています。
添加物の多い食材を減らす、アルミニウムの含有量が多い医薬品を見直すといった工夫が必要です。
※1参考元:厚生労働省「アルミニウムに関する情報」
※2参考元:一般社団法人 日本アルミニウム協会「日本人のアルミニウム摂取状況と最近の研究」
関連記事:パーキンソン病にいい食べ物と摂りすぎに気をつけたい食べ物
パーキンソン病を予防する食事はあるの?
パーキンソン病はゆっくり進行する病気のため、毎日の生活を意識的に過ごすことが大切です。
パーキンソン病を直接防いだり治したりする食材はありませんが、予防に効果が期待できる要素は次の5つです。
【パーキンソン病の予防が期待できる食事の要素】
- フェニルアラニン
- チロシン
- メチオニン
- 食物繊維
- カフェイン
ここからは、パーキンソン病を予防するための食事についてみていきましょう。
予防の食事①フェニルアラニンを含む食べ物
フェニルアラニンは、人体で合成できない「必須アミノ酸」の一種です。
神経伝達物質・ドーパミンの材料となる物質で、それ自体を体内で合成できないため、食材から補う必要があります。
フェニルアラニンが含まれる食材には卵や小麦が挙げられます。
ドーパミンの分泌量の低下が診断された場合は、フェニルアラニンを含んだ卵や小麦を意識的に摂るようにしましょう。
予防の食事②チロシンを含む食べもの
チロシンは、必須アミノ酸のフェニルアラニンから合成される物質です。
ドーパミンやアドレナリンの材料となり、体の代謝や自律神経の調整を行うホルモンにも作用します。
パーキンソン病を予防するためには神経伝達物質・ドーパミンの材料を食事などから補う必要があります。
チロシンはバナナやりんごに含まれるので、デザートに砂糖を多く含む甘いものではなく、バナナやりんごなどを取り入れるとよいでしょう。
予防の食事③メチオニンを含む食べもの
メチオニンは、硫黄を含む「含硫アミノ酸」で、体内で合成できない必須アミノ酸の一種です。
メチオニンが体内に入ると、滋養強壮の元になるタウリンや肝臓の機能を助けるグルタチオンに変化するため、フェニルアラニンの分解を促進させます。
カフェインを含むコーヒー飲料や香辛料(スパイス)に含まれています。
予防の食事④食物繊維が豊富な食べもの
近年の研究では、パーキンソン病の発症原因は腸も関係しているのではないかと考えられるようになっています。
腸の健康を保つためには、正常な便通が重要です。
食物繊維は、腸内の環境を整えて老廃物を押し出してくれます。
また、食物繊維が豊富な食べものの多くはローカロリーなので、炭水化物の摂りすぎも予防できます。
予防の食事⑤カフェインを含む飲みもの
2018年1月、順天堂大学および国立研究開発法人日本医療研究開発機構は、1日あたりカフェイン入りのコーヒーを1,2杯程度摂取するとパーキンソン病への予防効果が期待できるという研究結果を発表しました。(※)
カフェインを含む飲みものはコーヒー・紅茶・緑茶・ココアなどです。どれも日常的に飲用できる飲みもので、研究分野でもカフェイン補充治療の開発が進められています。
※参考元:順天堂大学「カフェインとその代謝産物がパーキンソン病診断のバイオマーカーになる~ 血液による診断とカフェイン補充治療への期待 ~」
関連記事:パーキンソン病は予防できる?主要な症状もあわせて解説
パーキンソン病の方におすすめの間食
パーキンソン病の方が厳密に制限されている食材はありませんが、動物性脂肪や糖質が多く含まれる食べものは避けたほうがよいとされています。
また、アルミニウムが含まれるベーキングパウダーやサプリメントなどの医薬品についても、摂取量に注意したいところです。
おすすめの間食メニューは、チロシンを含むバナナやナッツ類、チーズなどです。
飲みものにカフェインを含む緑茶やコーヒーを選び、神経伝達物質の材料を意識的に補充しましょう。
食事以外にパーキンソン病を予防する方法

食事以外の方法としては、心身に負担が大きくなる行動を避けるだけでも予防効果が期待できます。
ストレスをためない・適度に体を動かす・睡眠をきちんととる3つの行動を心がけてみてください。
予防法①ストレスをためない
パーキンソン病の症状悪化には、ストレスが関連しているといわれています。
明確な関連についてはわかっていませんが、ストレスの程度が強い人ほど、脳内のドーパミン欠乏が表面化しやすいと考えられているのです。
労働環境や家庭環境、その他の情緒的な問題によってストレスがかかると、パーキンソン病の発症リスクが高まる可能性があります。
予防法②適度に体を動かす
ストレッチや体操、ウォーキングのような軽い運動は、いずれも血流の循環を改善してストレスを発散する力があります。
定期的な運動は、神経細胞の保護や症状の進行を遅らせる効果が期待できるため、パーキンソン病の予防に有効です。
有酸素運動は、神経栄養因子の増加やミトコンドリア機能の改善にも有効といわれており、運動を習慣化することが大切です。(※)
※参考元:J-Stage「パーキンソン病のリハビリテーション治療」
予防法③睡眠をきちんととる
睡眠は脳内のドーパミン量を安定させて、パーキンソン症状の予防に効果が期待できます。
睡眠がしっかりとれれば疲れを残さず、日常生活の活動や運動が続けやすくなります。
神経伝達のバランスを安定させるためにも、普段から睡眠を意識的にとるようにしましょう。
「眠れないから」といって起き続けていると、脳や体には大きなストレスがかかります。
寝付きが悪いときでも、決まった時間に就寝するように工夫してみてください。
施設選びや介護にお悩みのかたはお気軽にご相談ください。
介護相談のプロがあなたのお悩みに寄り添い、最適な施設をご紹介いたします。
パーキンソン病の予防は食事から
今回は、パーキンソン病のリスクを高める食事と予防に役立つ栄養素や食材、その他の予防方法を紹介しました。
運動症状も含めて、パーキンソン病にはさまざまなトラブルがみられます。
睡眠障害のように、生活の質に影響するような障害をきたす場合もあります。
初期の段階では気づきにくく、ある程度進行してから気づくケースもみられるため、普段の生活から意識的に予防や改善を続けていくようにしましょう。
スーパー・コートではパーキンソン病専門住宅を運営しており、パーキンソン病のご入居者の運動機能の維持や生活の質の向上を目指した取り組みにも力を入れているので、ぜひご相談ください。
監修者

花尾 奏一 (はなお そういち)
介護主任、講師
<資格>
介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
<略歴>
有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。