
column
コラム
公開日: 更新日:
パーキンソン病で利用できる制度ともらえる助成金を解説

進行性の病気であるパーキンソン病では、薬物療法や手術で症状を緩和させるのが一般的です。
しかし、パーキンソン病の医療費は高額なため、国や自治体の支援制度なくしては、治療が続けられない方も多いはずです。
そこで本記事では、パーキンソン病患者の方が利用できる支援制度をお伝えします。
長期治療が必要な病気ですから、支援制度をうまく活用して、在宅介護や老人ホームへの入居にかかる費用を賄う際にお役立てください。
パーキンソン病とは
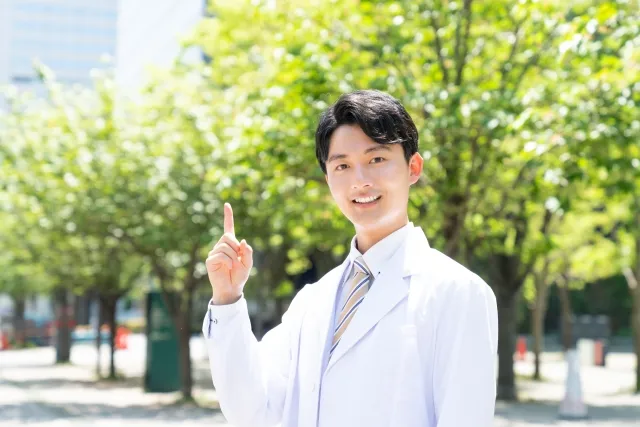
パーキンソン病とは、中脳にあるドーパミン神経細胞の減少により、ドーパミンの生成量が不足して発症するとされる病気のことです。
主に50~65歳の罹患者が多い傾向にありますが、まれに40歳前後で発症する若年性パーキンソン病のケースもみられます。
ドーパミンは、多幸感や快感を得たり、意欲を向上させたりするだけではなく、運動機能の調節にも関わる重要な神経伝達物質です。
これが減少してしまうと、気持ちの落ち込みや意欲の低下が表われ、さらに手足の震えや筋固縮、姿勢保持障害などの運動症状を発症するのです。
現在はまだ、パーキンソン病の根本的な治療法は確立されておらず、主に薬物療法によって症状を緩和させながら、長期的に病気と向き合っていく方法がとられています。
このことから、パーキンソン病は厚生労働省が定める、「指定難病」の対象疾患の一つに数えられています。
指定難病であるパーキンソン病患者の方が受けられるサポート
国から指定難病と認められたパーキンソン病患者の方には、国や自治体からいくつもの公的支援が提供されており、これらを利用することで医療費を大幅に減らせます。
継続的な治療を要するパーキンソン病の医療費は高額なうえ、症状がさらに進んで、介護サービスの利用や介護施設への入居が必要になると、そのための費用も工面しなければなりません。
ご本人やそのご家族にとって、こうした公的な支援制度の存在がいかに大きいものかがお分かりいただけるでしょう。
パーキンソン病は進行性で、かつ慢性的な病気であるがゆえ、少しでも長く安心して暮らすためには、指定難病の支援制度を利用して、金銭面での不安を払拭することが大切です。
この支援制度については、次の項で詳しくお伝えします。
関連記事:パーキンソン病の主な症状とは?診断の基準・検査方法も紹介
パーキンソン病患者の方が利用できる支援制度

ここからは、パーキンソン病患者の方が受けられる主な公的支援制度を紹介します。
難病医療費助成制度
パーキンソン病を患っている方は、難病医療費助成制度の対象となり、国から医療費の助成を受けられる場合があります。
この対象者を決める指標には、パーキンソン病の重症度を測る「ホーエン・ヤール重症度分類」と、「生活機能障害度分類」が用いられます。
前者は1~5度に、後者は1~3度に分類されており、「ホーエン・ヤール重症度分類3度以上かつ生活機能障害度2度以上」の方が、難病医療費助成制度の対象です。
例外として、上記の条件を満たさない場合でも、毎月の医療費総額が3万3,330円を超える月が年3回以上ある方は助成対象とみなされます。
助成金をもらうためには、各市区町村の専用窓口に、難病指定医が作成する診断書をはじめとした必要書類の提出が必須です。
申請が通ると、指定難病医療受給者証とあわせて、自己負担上限額管理票が交付され、これに記載された1か月の自己負担上限額を超えた部分の医療費が支給されます。
身体障害者福祉法
肢体不自由に該当するパーキンソン病患者の方は、身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳が交付され、各種支援を受けられます。
ただし、症状の程度によっては、対象から外れる可能性があるのでご注意ください。
この支援内容には、医療費の助成をはじめ、特別障害者手当などの経済的支援、おむつの支給や住宅改善資金助成といった生活面の支援、住民税や所得税の控除が含まれます。
なお、支援内容の詳細は各自治体によって異なるので、お住まいの地域で提供されている補助制度やサービスをあらかじめ確認しておきましょう。
介護保険制度
介護保険制度で介護サービスを受けられるのは65歳以上の要介護者ですが、特定疾病のパーキンソン病が原因で介護が必要になった40~64歳の被保険者も対象となります。
介護保険制度を利用するには、各自治体から要支援1~2、あるいは要介護1~5のいずれかに認定されていなければなりません。
要支援・要介護認定された場合は、有料老人ホームへの入居をはじめ、訪問介護や訪問リハビリテーションといった介護サービスを、1~3割程度の自己負担額で利用できます。
自己負担額の割合は、ご本人の年金収入やそのほかの所得金額、要介護度に応じて決定されます。
障害者総合支援法
18歳以上でパーキンソン病を患っている方なら、重症度にかかわらず障害者総合支援法の対象となり、日常生活を送るうえで総合的なサポートを受けられます。
ただし、介護保険制度の対象者は、そちらが優先的に適用されるため、障害者総合支援法はパーキンソン病の罹患者のなかでも若年層に的を絞った支援制度といえるでしょう。
主な支援内容には、介護給付や訓練等給付、地域相談支援給付が挙げられ、生活上で必要な支援から就労に関わる支援まで、幅広くサポートしてくれます。
これらのサービスを利用する際の自己負担額の上限は、個人の所得に応じて変動します。
医療保険制度・後期高齢者医療制度
公的医療保険に加入している75歳未満の方は医療保険制度を、75歳以上の方は後期高齢者医療制度をそれぞれ利用できます。
パーキンソン病は高齢者に発症する可能性が高いため、このような制度についてもきちんと理解しておくことが大切です。
医療保険制度では、病院の窓口に保険証を提示することで医療費の自己負担額が2~3割に減額されるのは、ご存じの方も多いでしょう。
一方、後期高齢者医療制度の対象者も、窓口へ後期高齢者医療被保険者証を提示すれば、自己負担額を1~3割に抑えられます。
このとき、後期高齢者医療制度の自己負担割合は、年金収入とそのほかの所得金額を合計した額によって設定されます。
成年後見制度
パーキンソン病の悪化により認知機能に障がいが表れ、判断能力が不十分となった場合、成年後見制度を利用すれば、成年後見人が法律行為に関する手続きを代行してくれます。
財産管理や生活上で必要な契約の締結などがこれに該当し、いわばご本人の「権利」を保護・支援する制度です。
成年後見制度には、すでに適切な判断を下せなくなった方が利用する「法定後見制度」と、将来、判断能力が低下した際に備える「任意後見制度」があります。
前者では家庭裁判所が後見人を選びますが、後者はご本人自らが任意で選出することが可能です。
上述の通り、この制度は、医療費や介護費の助成を受けるためのものではありません。
しかしながら、ご本人の財産の適切な管理なくしては、安心してパーキンソン病の闘病生活を送ることはできないので、非常に重要な公的制度といえます。
障害年金
ここまでに紹介した制度とはやや毛色が異なりますが、肢体不自由なパーキンソン病患者の方は、障害年金の受給対象として認められ、金銭的な援助を受けられる場合があります。
ただし、この制度を利用するには、3つの要件を満たさなければなりません。
【パーキンソン病で障害年金を受給するための要件】
- パーキンソン病の治療を受けた初診日において、65歳未満である
- 初診日の前日において、前々月までの1年間に年金保険料の未納期間がない
- 障害等級の認定基準に該当している
上述した障害等級の認定基準を、日本年金機構が定める「障害等級基準」より一部抜粋してお伝えしますので、ご参照ください。
障害等級の認定基準
| 障害等級 | 障害の状態 |
| 1級 | 身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であり、日常生活に支障をきたす程度のもの |
| 2級 | 身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であり、日常生活に著しい制限を受ける、あるいは制限を設けることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を設けることを必要とする程度のもの |
これらの条件を満たしているパーキンソン病患者の方は、障害年金を受け取れます。
また、障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つに大別されているため、それぞれで受給できる額については、以下で詳しく解説します。
参照元:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第4 肢体の機能の障害
障害基礎年金でもらえる額
パーキンソン病で、障害等級1級、あるいは2級に認定された場合は、諸条件を満たしていれば、障害基礎年金を受け取ることが可能です。
その際の等級ごとの支給額は、以下の通りです。
障害基礎年金の支給額
| 障害等級 | 金額 |
| 1級 | 102万円/年+子の加算 |
| 2級 | 81万6,000円/年+子の加算 |
障害基礎年金は、受給権を得た翌月から支給が始まり、全額を6等分した額が2か月に一度口座に振り込まれます。
また、子の加算における「子」とは、18歳に到達した年度の末日を経過していない、一般的には高校卒業までのお子さまのことです。
2人目までは1人につき23万4,800円が、3人目以降は1人につき7万8,300円が上乗せされます。
障害厚生年金でもらえる額
障害等級1~3のいずれかに該当する場合、障害厚生年金の対象となり、障害基礎年金に上乗せされるかたちで受給できます。
このとき、障害基礎年金の対象に3級は含まれないため、障害厚生年金のみが支給されることになります。
パーキンソン病患者の方が受け取れる、等級ごとの障害厚生年金の額を表にまとめましたので、ご確認ください。
障害厚生年金の支給額
| 障害等級 | 金額 |
| 1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(23万4,800円) |
| 2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(23万4,800円) |
| 3級 | 報酬比例の年金額(最低保証額61万2,000円) |
上記を踏まえると、老齢年金の定額部分である基礎年金に上乗せされる、報酬に応じた年金額、すなわち報酬比例部分を基準としていることが分かります。
その際、障害等級1~2級と認定された方に生計を維持されている、65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金額が加算される仕組みです。
このことから、障害厚生年金で受給できる額は、給与や働いていた期間、配偶者の有無によって左右されるため、個人差が大きいといえるのです。
パーキンソン病の介護ならスーパー・コートのパーキンソン病専門住宅がおすすめ
これまでに紹介した支援制度を有効活用しつつ、それでもパーキンソン病の方の在宅介護が困難になった際には、有料老人ホームスーパー・コートへの入居がおすすめです。
また、特別養護老人ホームへの入居を希望していて、待機者が多数で入居日の見通しが立たない方も、スーパー・コートを選択肢に加えてみてください。
スーパー・コートでは、建物の設計から介護体制に至るまで、すべてをパーキンソン病患者の介護に特化した「パーキンソン病専門住宅」を保有しています。
専門医による医療体制と、24時間の看護体制を整え、患者さまが安心して暮らせる住まい造りを実現しました。
この施設で働くスタッフは、パーキンソン病に関する豊富な知識を有しており、患者さまに合わせた最適な介護を提供することが可能です。
患者さま一人ひとりと真摯に向き合うため、ご本人においては身体的、精神的な不安を払拭でき、ご家族も心身を癒す時間を確保できるはずです。
パーキンソン病は進行性の病気ですから、ご本人とご家族が継続的に平穏な生活を送るためにも、スーパー・コートのパーキンソン病専門住宅への入居をぜひご検討ください。
関連記事:老人ホームの入居費用はいくら?タイプ別の費用相場と払えない時の対処法
パーキンソン病患者の方は、支援制度で助成金をもらうことで経済的な負担を軽減できる
今回は、パーキンソン病患者の方が利用できる支援制度をお伝えしました。
国から指定難病と認められているパーキンソン病を患っている方は、治療や生活上のさまざまな支援を受けられます。
パーキンソン病にかかる医療費は高額なため、このような支援制度を有効活用すれば、経済的な負担を軽減でき、継続的な治療が可能です。
支援制度を活用しつつも、在宅での生活が難しくなったら、そのときは有料老人ホームスーパー・コートへの入居がおすすめです。
パーキンソン病患者の方の介護に特化した専門住宅で、徹底的に寄り添ったサービスを提供していますので、ご本人とご家族の穏やかな暮らしをお望みの方は、ぜひお問い合わせください。
監修者

花尾 奏一 (はなお そういち)
介護主任、講師
<資格>
介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
<略歴>
有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。











