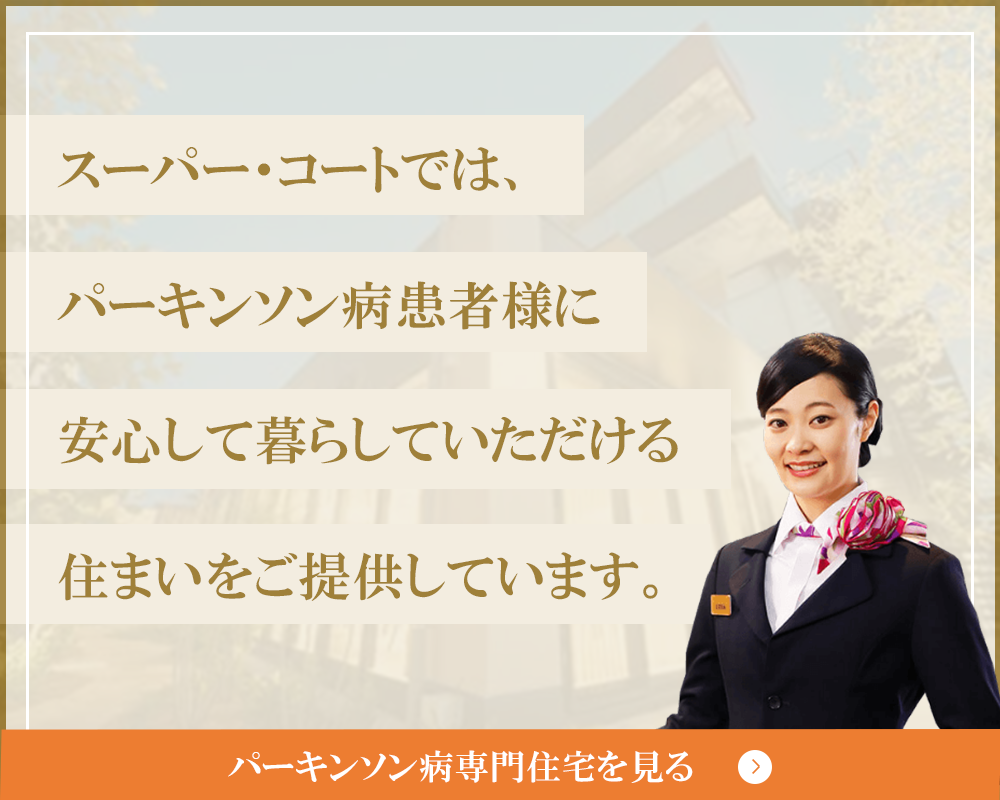column
コラム
公開日: 更新日:
レビー小体型認知症の原因は?注意すべき症状や発症しやすい人の特徴

認知症の一種であるレビー小体型認知症は、アルツハイマー型認知症や血管性認知症と並び、三大認知症と呼ばれています。気になる症状があり「レビー小体型認知症かもしれない」と心配している方もいるのではないでしょうか。
そこで、レビー小体型認知症について調べている方のため、特徴や原因、主な症状などを紹介します。この記事を読むことでどのような人が発症しやすいのか、どのような対応をしていけばいいのかなどもわかるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。
レビー小体型認知症とは?
レビー小体型認知症は、病名の由来となっている「レビー小体」というタンパク質のかたまりが脳に蓄積し、神経細胞が減少することで発症する認知症です。
病気を根本的に治療する方法はまだ見つかっていません。しかし、早期発見・早期治療を行うことで、症状の進行を遅らせたり、緩和したりすることが可能なため、まずは早期発見が重要です。
レビー小体型認知症の特徴
大きな特徴として挙げられるのが、認知機能障害のほかにパーキンソン症状を伴うことが挙げられます。
どの程度の症状が現れるかは人それぞれではありますが、幻視・幻聴、抑うつ症状、睡眠障害、自律神経症状と、症状の幅が広いのも特徴です。
人によっては、認知症機能障害よりもその他の症状が強く出てしまうことがあり、こういった場合は他の病気と誤診されてしまうケースもあります。レビー小体型認知症の診断が得意な病院での相談が必要です。
レビー小体型認知症の原因
レビー小体型認知症の主な原因として挙げられるのが「レビー小体」の蓄積です。レビー小体は英語で「Dementia with Lewy bodies」と表現することから、その頭文字を取って「DLB」とも呼ばれます。
αシヌクレインというタンパク質のかたまり方が異常な状態になることで、さまざまな症状を引き起こします。
レビー小体が蓄積する具体的な原因は、まだはっきりとわかっていません。しかし、脳の加齢による変化が一因と考えられています。
レビー小体型認知症の特徴の一つにパーキンソン症状があります。これは、パーキンソン病と同様に、脳内にレビー小体が形成されることが関係しています。
パーキンソン病の主な症状として、震えや動きが遅くなる、筋肉がこわばるなど症状が挙げられます。パーキンソン病の大きな原因は、運動機能などの調整と関わり合いのあるドーパミンと呼ばれる神経細胞の減少です。
レビー小体が蓄積すると、ドーパミンを生成する神経細胞が減少し、ドーパミンが不足することで、パーキンソン症状が現れます。
レビー小体型認知症でみられる症状
レビー小体型認知症を発症すると、どのような症状が現れるのかを紹介します。代表的な症状について、以下で詳しく解説します。
幻視・幻聴
実際にはそこにないはずのものが見えたり、聞こえたりする幻視・幻聴は、レビー小体型認知症の代表的な症状の一つです。
たとえば「家の中に知らない人が座っている」「壁に虫がいる」などの幻視が現れます。家族には幻であるとわかりますが、本人にははっきりと見えているため、強い恐怖を感じることがあります。
なお、幻視・幻聴はアルツハイマー病ではあまりみられないため、レビー小体型認知症とアルツハイマー病を見分けるポイントの一つになります。
抑うつ症状
抑うつ症状とは、気分が落ち込みがちになり、無気力になったり、ぼーっとしたりする症状のことです。これまで熱中していた趣味に興味が持てなくなったり、一日中座って過ごしたりする人もいます。
症状によっては、不眠や食欲不振がストレスや体力低下につながることもあるため、気になる症状があれば医師に相談してください。
睡眠障害
睡眠障害の一つに、レム睡眠行動異常症があります。睡眠は、眠りの浅いレム睡眠と眠りの深いノンレム睡眠を繰り返します。
レム睡眠行動障害とは、レム睡眠時に異常行動を取ってしまう症状です。
たとえば、夢と連動する形で突然大きな声を上げる、暴れるなどの行動がみられます。寝ぼけて少し動くというよりも激しい動作になることがあるため、寝床の周囲にはできるだけものを置かないようにしてケガを防ぐ備えをしておきましょう。
自律神経症状
自律神経症状として、立ちくらみや便秘、寝汗の増加などがみられます。身体のだるさを感じたり、人によっては失神したりするケースもあります。
自律神経には活動時に活発に働く交感神経とリラックスする際に働く副交感神経の2種類があるのですが、これらのバランスが崩れることで起こるのが自律神経症状です。レビー小体型認知症の初期段階からみられることもあります。
パーキンソン症状
レビー小体型認知症の中でも特徴的な症状として挙げられるのは、パーキンソン病と似た症状が現れるパーキンソン症状です。
たとえば、筋肉や関節をうまく動かせなかったり、手足の震えがみられたりします。他にも、動作がゆっくりになったり、小さくなったりすることもあります。
パーキンソン症状の中でも特に注意が必要なのは、転倒リスクの上昇です。筋肉をうまく動かせなくなることにより、姿勢を崩した際にうまく立ち直せなかったり、歩行にトラブルが生じたりすることもあります。
転倒によるケガや骨折が原因で体力が低下し、寝たきりになるリスクもあるため、十分な注意が必要です。
レビー小体型認知症を発症しやすい人はいる?
レビー小体型認知症を発症しやすい人には、いくつかの共通点があります。
主な特徴は以下の5つです。
65歳以上の方
レビー小体型認知症は、加齢とともに発症リスクが高まります。早い方だと30代で発症する方もいますが、特に注意が必要なのは、65歳以上の方です。
高齢になるとさまざまな不調を感じやすくなり、それが複合して現れることもあります。
そのため、レビー小体型認知症に該当する症状が現れても、なかなか直結させて考えるのは難しいといえるでしょう。ただ、高齢になるほどリスクが高まるため、その点を理解しておくことが大切です。
男性の方
女性よりも男性の方が発症するリスクが高く、その確率は女性の2倍ほどといわれています。(※)
65歳以上の男性はそうでない人よりも注意が必要です。なお、認知症というとアルツハイマー型認知症が有名ですが、こちらは女性に多い特徴を持っています。
(※)
精神的な問題を抱えている方
精神的な問題を抱えている方は、そうでない方と比べてリスクが高いといわれています。
たとえば、慢性的なストレスを感じている、うつ病を患っているという方は特に注意しなければなりません。
脳卒中を経験した方
過去に脳卒中を経験した人もリスクが高いため、注意が必要です。脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで発生する病気であり、これにより身体が正常に動かなくなります。
脳卒中によって脳の血流が悪くなると、脳の神経細胞がダメージを受けてしまうことがありますが、脳の神経細胞の損傷はレビー小体型認知症を発症する大きな原因です。
認知症のご家族がいる方
家族に認知症の方がいる場合、発症リスクが高まることがあります。
たとえば、アルツハイマー型認知症のリスクを高めるAPOE遺伝子のうち、APOE4は特に強力な遺伝的危険因子とされています。
このAPOE4は、レビー小体が脳に蓄積しやすくなる可能性があると考えられています。(※)
そのため、認知症のご家族がいる方はAPOE4を持っている可能性があり、レビー小体型認知症のリスクも高まると考えられています。
(※)
参考:(PDF)公益財団法人 長寿科学振興財団:エイジングアンドヘルス[PDF]
レビー小体型認知症は予防できるのか
予防策を講じたとしても、レビー小体型認知症の発症を完全に防ぐことはできません。ですが、生活習慣を整えたり、人とコミュニケーションを取ったりすることが予防につながるとされています。
まず、健康的な生活習慣を意識しましょう。健康に良くないとされることは意識的にやめていくことも重要です。
また、脳に関する病気ということもあり、脳を活性化させていくことも大切とされています。
いろいろな人と話したり遊びに行ったりするのも良いでしょう。また、読書やクロスワードパズルのように脳を使った趣味を見つけてみるのもおすすめです。
レビー小体型認知症のセルフチェックリスト
もしかしたらレビー小体型認知症かもしれないと疑った場合、どうすればいいのでしょうか。ここでは、注意したい症状をまとめたチェックリストを用意しました。
以下のうち、どの程度該当するものがあるか確認してみてください。
| 認知症状 | 物忘れ症状 |
| 問題解決や分析的思考が難しい | |
| マルチタスクや計画を立てる、順序を守るといったことが難しい | |
| 集中力・注意力のレベルの低下 | |
| まとまりのない発話や会話 | |
| 説明できない混乱が起こる | |
| ものとの距離がつかめなくなる | |
| パーキンソン症状 | 硬直やこわばり |
| 引きずり歩き | |
| バランスが取れない、転倒を繰り返す | |
| 身体の震え | |
| 動作の遅さ | |
| 声の弱さ | |
| 筆跡の変化 | |
| 表情が変化しにくくなる | |
| よだれが出る | |
| 嗅覚の喪失または低下 | |
| 姿勢の変化 | |
| 行動と気分の変化 | 幻覚(実際には存在しないものが見えたり聞こえたりする) |
| 触覚、嗅覚に関するその他の幻覚症状 | |
| うつ病の症状 | |
| 無関心 | |
| 誤った信念などの妄想 | |
| 不安 | |
| 睡眠障害 | 睡眠中に時には激しく身体が動く、ベッドから落ちる |
| 日中の過度の眠気 | |
| 不眠症 | |
| むずむず脚症候群 | |
| 自律神経機能障害 | めまい、ふらつき、失神、または血圧の変化 |
| 暑さや寒さに敏感 | |
| 性機能障害 | |
| 尿失禁 | |
| 便秘 | |
| 原因不明の失神または一時的な意識喪失 |
参考:Lewy Body Dementia Association:COMPREHENSIVE LBD SYMPTOM CHECKLIST
該当するものが多いほど、レビー小体型認知症のリスクが高いといえます。また、レビー小体型認知症ではない場合でも、認知症状に多く該当する場合は、認知症の可能性があるかもしれません。
紹介したように、精神的な問題を抱えている方はレビー小体型認知症を発症する確率が高まります。
不安を抱えながらの生活が精神的な問題につながってしまうこともあるので、気になる症状の原因が何かはっきりさせるためにも一度病院で診察を受けてみてはいかがでしょうか。
レビー小体型認知症の可能性が高まるときにできること
レビー小体型認知症を心配している方は、日常生活の中でできる工夫に取り組んでいきましょう。以下のようなことが挙げられます。
定期的に医療機関を受診する
レビー小体型認知症などの認知症は、なかなか自身で気付けません。そこで、医療機関を受診して適切な検査を受けることが求められます。
レビー小体型認知症は進行性の病気ということもあり、一度発症するとその進行を止めるのは非常に難しいことです。そのため、仮に発症してしまった場合は早期治療に取り組んでいくことが大切といえます。
定期的に医療機関を受診することで、レビー小体型認知症の早期発見・早期治療が可能になります。
生活習慣を整える
たとえば、食事の内容に問題がある方もいるのではないでしょうか。野菜をほとんど食べていなかったり、揚げ物ばかりだったりする場合は見直してみてください。
健康的な生活習慣を意識することは、レビー小体型認知症だけでなく、さまざまな病気の予防にもつながります。
それから、運動習慣を作るようにしましょう。身体を動かすことで血流が良くなるため、脳に必要な酸素や栄養が行き渡りやすくなります。激しい運動を無理に行う必要はありません。
まずは、ウォーキングなどの続けやすいものを選択してみると良いかもしれません。
ウォーキングが難しい場合は、ストレッチを取り入れてみましょう。自宅でできる簡単なストレッチやヨガから始め、少しずつ運動習慣を身につけていくことをおすすめします。
ただし、運動時の転倒によって骨折やケガをすると、そこから寝たきりになってレビー小体型認知症を発症してしまう可能性もあるため、運動時は転ばないように注意が必要です。
ストレスを発散する
ストレスを抱え込むことにより、精神的な問題につながりやすくなります。身体だけではなく、心も健康的な状態に整えていきましょう。
ストレスを溜め込んでいることに気付けないこともあります。そのため、定期的にストレスを発散することを意識しましょう。
趣味を思いっきり楽しんだり、のんびり過ごしたりするだけでもストレス発散につながります。人によって適したストレス発散方法が異なるので、自分にとって楽しく感じられる方法を実践してみてください。
レビー小体型認知症の治療方法
レビー小体型認知症の治療法には、薬物療法、リハビリ、手術などがあります。
症状が非常に重い場合などは手術を検討することになりますが、その前に実践していくのが主に薬物療法とリハビリです。これについて解説します。
薬物療法
レビー小体型認知症を根本的に治療する方法はまだ見つかっていないことから、病気の進行を食い止めたり、症状を緩和したりする目的で薬物療法が行われます。
使用される薬は、患者さんの症状に合わせたものです。
薬物療法で注意しなければならないのが、レビー小体型認知症の患者さんは向精神薬に対して反応が過敏になることがあります。そのため、少量ずつ、時間をかけて適切な量を見極めていくことになります。
向精神薬とは、うつ病や統合失調症、神経症、不眠症をなどの治療に使われる薬ですが、副作用でパーキンソン症状が強く表れてしまうことがあります。
レビー小体型認知症はパーキンソン症状を抱える病気であるため、特に注意していかなければなりません。
また、反対に抗パーキンソン病薬は精神症状の悪化を招くことがあるため、薬剤の調整は難しいといえるでしょう。
場合によってはアルツハイマー型認知症の治療薬が使われることもあります。
こういった難しさもあるため、レビー小体型認知症の治療が得意な医療機関に相談することが重要です。
リハビリ
リハビリを行うことで筋力・体力を維持したり、脳の活性化が期待できたりします。
たとえば、通所施設や医療施設で実施される作業療法は効果的です。専門家はそれぞれの患者さんの状態に合わせて適切なプログラムを作成し、取り組んでいきます。
また、認知症の症状が出ても昔の記憶は鮮明に残っていることが多いため、過去の体験や楽しかった思い出を会話の中で引き出す回想法は、代表的なリハビリの一つです。
リハビリ施設では、語学療法やアロマセラピーが行われることもあります。
なお、運動する際と同様にリハビリ時も転倒に注意が必要です。
施設選びや介護にお悩みのかたはお気軽にご相談ください。
介護相談のプロがあなたのお悩みに寄り添い、最適な施設をご紹介いたします。
症状を知り早期発見につなげよう
今回は、レビー小体型認知症について紹介しました。レビー小体型認知症の概要や、発症しやすい人の特徴について理解を深められたのではないでしょうか。
代表的な症状を知ることは、早期発見につながります。
認知症やパーキンソン症状が強くなると、日常生活の中で不便さを感じることもあるはずです。有料老人ホームスーパー・コートでは、パーキンソン病に対応する施設も運営しており、専門的なサポートを行っています。
毎日充実した生活が送れるように認知症ケアにも取り組んでいるので、ぜひご相談ください。
監修者

花尾 奏一 (はなお そういち)
介護主任、講師
<資格>
介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
<略歴>
有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。