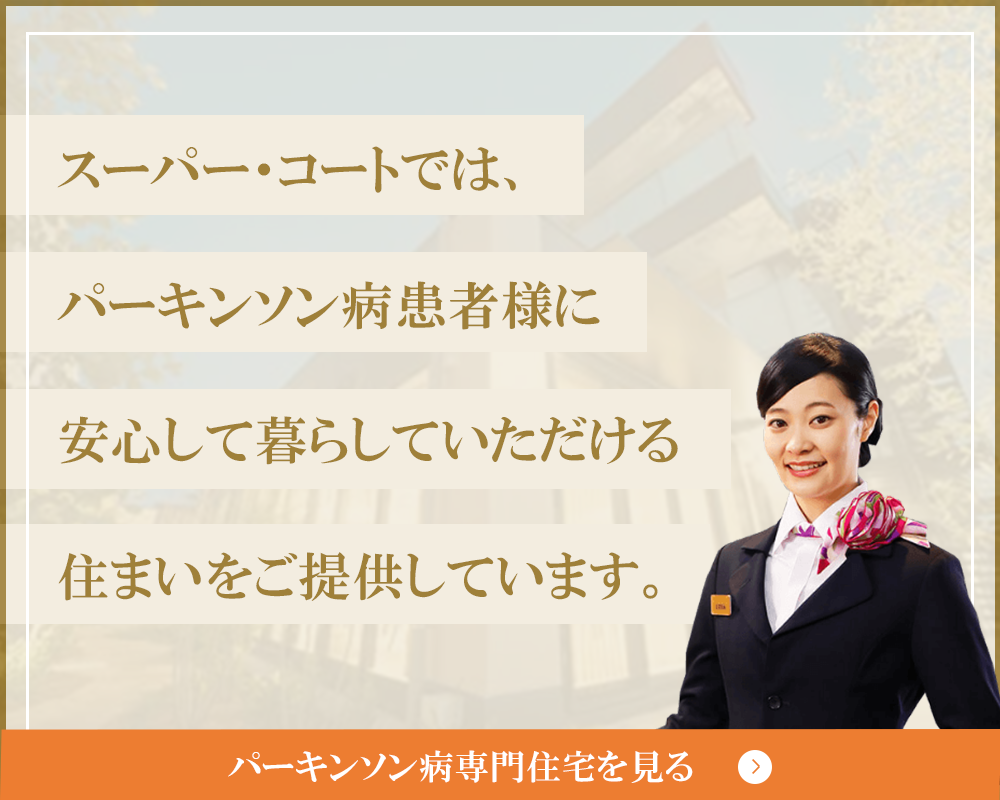column
コラム
公開日: 更新日:
レビー小体型認知症とは?原因&症状から治療まで徹底解説!

一口に認知症といっても、さまざまな種類があり、どの種類に該当するのかによって原因や症状、対処法などが異なります。認知症の種類の一つであるレビー小体型認知症について「どんな症状が出るの?」「もしかしたら自分がそうかもしれない」と、疑問に感じたり、不安を抱えていたりする方もいるでしょう。
そこで、レビー小体型認知症について詳しく知りたい方のため、概要や原因、症状などを紹介します。この記事を読むことで、レビー小体型認知症について理解を深めることができます。セルフチェックも用意しているので、ご自身の状態を確認する際に活用してください。
レビー小体型認知症とは?
レビー小体型認知症とは、認知症の症状としてよく知られる認知機能障害のほかに、せん妄や抑うつ、パーキンソン症状といったさまざまな症状がみられる種類の認知症です。
英語だと「Dementia with Lewy bodies」、略して「DLB」と呼ばれます。アルツハイマー型認知症、血管性認知症、そしてレビー小体型認知症の3つが三大認知症として知られていますが、認知症全体において、レビー小体型認知症が占める割合は約20%とされています。(※)
(※)
レビー小体型認知症の特徴
レビー小体型認知症は、女性と比較して男性の発症率が約2倍高く、他の認知症よりも進行が早い特徴があります。(※)
また、パーキンソン症状が現れることも、レビー小体型認知症の大きな特徴の一つです。
まだ根本的にレビー小体型認知症を治療する方法は発見されていません。ただ、適切な治療によって進行を遅らせることができます。
(※)
レビー小体型認知症を発症する原因
レビー小体型認知症の原因は、タンパク質であるαシヌクレインが神経細胞内に蓄積することにより、神経細胞が破壊されることにあります。このタンパク質αシヌクレインのかたまりが「レビー小体」です。
レビー小体型認知症はパーキンソン症状を伴う認知症であり、レビー小体はパーキンソン病の原因でもあります。
レビー小体型認知症が現れる主な原因は、加齢による脳の変化です。加齢に伴って少しずつ神経細胞が減っていきますが、これによって記憶や情報処理に関連した脳の部位が萎縮することにより、幻視や認知機能障害などが起こると考えられています。レビー小体型認知症の症状については、後ほど詳しく解説します。
レビー小体型認知症とほかの病気の違い
レビー小体型認知症は、認知症の一種であり、代表的なものとしてアルツハイマー型認知症が挙げられます。また、パーキンソン病と同様の症状が出ることでも知られているのですが、アルツハイマー型認知症とパーキンソン病とはどのような違いがあるのでしょうか。
以下に、それぞれの違いを解説します。
アルツハイマー型認知症との違い
アルツハイマー型認知症は、記憶障害を中心とした症状が現れる種類の認知症です。一方、レビー小体型認知症の場合は幻視やパーキンソン症状といったものであり、特にパーキンソン症状についてはアルツハイマー型認知症にはほとんどみられません。
また、レビー小体型認知症は認知機能障害にムラがあり、調子の良いときと悪いときがある点が特徴です。
それから、徘徊についてはレビー小体型認知症ではそれほどありませんが、アルツハイマー病の場合は主な症状の一つでもあります。
パーキンソン病との違い
レビー小体型認知症はパーキンソン症状を伴う認知症であり、パーキンソン病は筋肉のこわばりや手足の震えといった運動機能に障害が現れる病気です。
パーキンソン病単独の場合、必ずしも認知症を伴うわけではありません。ただ、進行期になると認知機能障害を発症することが増え、パーキンソン病認知症と呼ばれるものを発症することがあります。
レビー小体型認知症とパーキンソン病認知症は症状が似ているため、判別が難しい場合があります。
どちらの病気でも、神経細胞内にレビー小体が認められます。
参考:MSDマニュアル:レビー小体型認知症とパーキンソン病認知症
レビー小体型認知症の症状
レビー小体型認知症を発症すると、どのような症状が現れるのでしょうか。主な症状は、認知機能の低下、せん妄、抑うつ、パーキンソン症状の4つです。以下に、それぞれの症状について解説します。
認知機能の低下
レビー小体型認知症では、徐々に認知機能が低下します。認知機能は、物事を考えたり判断したりする際に欠かせないものです。
また、計算や理解、学習など、さまざまなものとも深く関係しています。
これらは日常生活において必要となるものなので、認知機能が低下すると日々の生活が不便になることもあるでしょう。ただ、特に初期段階のレビー小体型認知症では、認知機能障害が起こっていたとしても症状の出方や強さに大きなムラがある特徴を持っています。
そのため、認知機能障害の症状が強く出ているときに家族が認知症を疑ったとしても、症状が一時的に治まったときに「気のせいだったかもしれない」と考えてしまい、受診が遅くなってしまうこともあるようです。
せん妄
せん妄とは、意識混濁がみられる精神症状です。頭の中が混乱した状態になってしまい、幻視や幻聴がみられることがあります。
幻視とは幻を見ることであり、実際にはそこに存在していない人や虫、動物などがはっきりと見えてしまうのが特徴です。混乱・興奮して歩き回ったり「すぐそこに知らない人が座っている」「木の柱が人の顔に見える」と怯えたりしてしまうこともあります。
レビー小体型認知症では徐々に認知機能が低下しますが、初期段階では症状がそれほど強く現れないため、病気の早期発見には幻視に気づくことが重要です。
人によって幻覚の出方は異なり、場合によっては聞こえないはずのものが聞こえてしまう幻聴の症状が出ることもあります。
抑うつ
気持ちが落ち込みがちになり、何をするにしても意欲が失われてしまうのが、抑うつです。生きることさえつらく感じたり、些細なことでも深く悲しんだりすることがあります。
これまで意欲的に取り組んでいたことでも、突然やる気を失い、家族に心配されることがあります。
レビー小体型認知症の患者の中には、認知機能障害がほとんど見られず、抑うつ症状が強く現れることがあります。このような場合、うつ病と診断されることもあります。また、元気がなくなるだけではなく、食事量が減ったり、一日中ぼーっと過ごすことが増えたりします。
パーキンソン症状
レビー小体型認知症では、パーキンソン病に似た症状が現れることがあります。代表的な症状として、手足の震えや筋肉のこわばり、動作が小さくなること、姿勢を崩した際に立て直せず転倒することが挙げられます。
特に高齢者の場合は、パーキンソン症状によって転倒したことが原因で骨折し、そこから急激に体力や筋力が落ちてしまうこともあります。場合によっては寝たきりの状態になることも考えられるため、注意しておかなければなりません。
症状の現れ方には個人差がありますが、認知機能障害の前にパーキンソン症状が出ると、パーキンソン病と診断されることがあります。
パーキンソン病と診断されて薬を飲んでいるもののなかなか良くならないということであれば、レビー小体型認知症の可能性もあることから、再度かかりつけ医に相談してみてください。
レビー小体型認知症の進行段階
病気の中には少しずつ進行していくものもありますが、レビー小体型認知症は、調子の良い日と悪い日を繰り返しながら、徐々に悪化していく特徴があります。
「昨日は驚くほど認知症の症状が出ていたのに、今日は全く出ない」といったことも珍しくありません。
初期症状として現れることがあるのは、うつ症状や睡眠関係の異常、臭いがわかりにくくなる嗅覚異常などです。一般的には、そのあとに物忘れやせん妄、パーキンソン症状など、レビー小体型認知症特有の症状が現れるようになります。
初期段階では大きな変化が少ないため、気づきにくいことがあります。しかし、初期症状を知っておくことで早期発見につなげやすくなります。
中期以降になると目立ち始めるのが認知機能障害の症状です。初期段階では症状に波があり、調子の良い日と悪い日を繰り返します。その後、中期以降になると調子の悪い日、悪い時間帯が増えていくようになります。
せん妄や徘徊、パーキンソン症状が悪化していくのも中期以降です。このころから周囲のサポートを必要とすることが増えていきます。
末期段階まで進行した場合は、認知機能障害が悪化するほか転落や誤嚥のリスクも高まることから、常時介護が必要です。
また、徘徊や、物を盗られたなどの妄想が起こることもあるため、介護者はこのあたりのこともしっかりと理解しておかなければなりません。
初期状態から常に介助を必要とする状態になるまでにかかる時間は、10年未満といわれています。
ただし、進行速度には個人差があるため、一概には判断できません。あくまで参考として考えましょう。
レビー小体型認知症の早期発見につながるセルフチェックリスト
レビー小体型認知症は、できるだけ早期に発見し、治療を開始することが重要です。そこで、早期発見につなげるためのチェックリストを確認しておきましょう。
次のうち、該当するものがどの程度あるか確認してみてください。
| 認知症状 | 物忘れ症状 |
| 問題解決や分析的思考が難しい | |
| マルチタスクや計画を立てる、順序を守るといったことが難しい | |
| 集中力・注意力のレベルの低下 | |
| まとまりのない発話や会話 | |
| 説明できない混乱が起こる | |
| ものとの距離がつかめなくなる | |
| パーキンソン症状 | 硬直やこわばり |
| 引きずり歩き | |
| バランスが取れない、転倒を繰り返す | |
| 身体の震え | |
| 動作の遅さ | |
| 声の弱さ | |
| 筆跡の変化 | |
| 表情が変化しにくくなる | |
| よだれが出る | |
| 嗅覚の喪失または低下 | |
| 姿勢の変化 | |
| 行動と気分の変化 | 幻覚(実際には存在しないものが見えたり聞こえたりする) |
| 触覚、嗅覚に関するその他の幻覚症状 | |
| うつ病の症状 | |
| 無関心 | |
| 誤った信念などの妄想 | |
| 不安 | |
| 睡眠障害 | 睡眠中に時には激しく身体が動く、ベッドから落ちる |
| 日中の過度の眠気 | |
| 不眠症 | |
| むずむず脚症候群 | |
| 自律神経機能障害 | めまい、ふらつき、失神、または血圧の変化 |
| 暑さや寒さに敏感 | |
| 性機能障害 | |
| 尿失禁 | |
| 便秘 | |
| 原因不明の失神または一時的な意識喪失 |
参考:Lewy Body Dementia Association:COMPREHENSIVE LBD SYMPTOM CHECKLIST
睡眠障害の中にあるむずむず脚症候群とは、レストレスレッグス症候群とも呼ばれるものです。
特に足に異常な感覚が発生し、ムズムズする、痛がゆいなどの症状が現れ、じっとしていられなくなります。結果として眠気を感じても眠れず、不眠になってしまうことがあります。(※)
上記チェックリストで該当するものがいくつかある場合は、医師に相談してください。
(※)
参考:e-ヘルスネット:レストレスレッグス症候群 / むずむず脚症候群
レビー小体型認知症の検査・診断方法
レビー小体型認知症が疑われる場合、どのような検査・診断が行われることになるのでしょうか。
ここでは、代表的な検査・診断方法について紹介します。
血液検査
血液検査は、その他の病気である可能性を調べるために行うものです。たとえば、甲状腺機能低下症である場合は精神活動性が低下することから、レビー小体型認知症と同様に認知症の症状が現れることがあります。
血液検査を行うことで、甲状腺機能低下症の有無を判断できます。他に、ビタミンB12欠乏症などでも認知症の症状が現れることがあるため、これらの病気の可能性を排除するために血液検査を行います。
脳波検査
補助的な目的で行われることがあるのが、脳波検査です。レビー小体型認知症では側頭葉の脳波に特徴的な動きがみられることもあるため、それらが起こっていないかを検査します。
症状を特定するために用いられる検査です。
神経心理検査
症状がみられている本人に対し、質問やテストを行う検査です。なかでも、ミニメンタルステート検査(MMSE:Mini-Mental State Examination)という検査がよく用いられています。
検査時間は6〜10分程度で、11項目・30点満点の問題で構成されています。詳細は以下のとおりです。
| 時間の見当識1点×5個 | 季節や日付などに関する検査。季節は「春夏秋冬」のほか「梅雨」や「初夏」などでも正解になるものの、日付は1日でも間違った場合は不正解。 例:「今日は何日ですか?」「今の季節は?」 |
| 場所の見当識1点×5個 | 現在自分がいる場所を正確に理解できているかに関する検査。施設名称については通称や略称でも認められる。 例:「ここはなんという施設ですか?」 |
| 3単語の即時再生1点×3個 | 短い記憶を保てているか確認するための検査。出題者が1秒1つずつ3つの言葉を伝え、繰り返し答えてもらう。3つすべて答えられるまで行う。6回繰り返した段階で答えられなかった場合は終了。その時点で言えた単語の数で評価する。 例:「鉛筆、水筒、猫」 |
| 計算5点 | 暗算での引き算、または逆から単語をいう問題。問題は5回繰り返される。計算を間違えた場合や、答えられない場合はそこで中止となる。 例:「100から7を引いてください、そこからまた7を引いてください」 |
| 遅延再生1点×3個 | 3単語の即時再生で覚えた単語を回答する。順番は問わず、出題者がヒントを出しても問題ない。 |
| 物品呼称1点×2個 | 誰もが知っているものの名称を思い出せるか確認する検査。2つの物品を1つずつ見せて答える。 例:「(時計を見せながら)これはなんですか?」 |
| 文章復唱1点 | 質問者からある程度の長文が口頭で伝えられて、それを繰り返せるか調べる検査。一度で正しく答えられた場合は1点となり、少しでも間違えたら不正解となる。 例:「みんなで、力を合わせて綱を引きます」 |
| 3段階の口頭命令1点×3段階 | 複数の指示を出し、それを理解して実践できるか調べるための検査。3段階の指示が出される。耳が聞こえにくい場合は指示を繰り返すことも認められる。 例:「ここにあるペンを右手に持ってください」「そのペンを左手に持ち替えてください」「私に渡してください」 |
| 書字命令1点 | 文字で書かれた文章を理解し、実行できるかを調べる検査。紙に書いた文章を読み、その指示を実行する。 例:「下を向いてください」 |
| 文章書字1点 | 文章を書く力を調べる検査。どのような内容でも構わないものの、意味の通じる内容であることが必須。単語のみでは不正解となる。 |
| 図形模写1点 | ある図形を見せられたあとに同じものを書く検査。交差する2つの5角形の図形を模写できれば正解。図形が交差していない場合や五角形が描けていない場合などは不正解となる。 |
テストの結果、23点以下は認知症疑いと判断され、27点以下であった場合は軽度認知障害が疑われることになります。(※)
(※)
参考:一般社団法人 日本老年医学会:認知機能の評価法と認知症の診断
画像による検査
各種機器を用いて画像検査を行います。たとえば、脳の内部の様子を確認するMRI検査・CT検査が有名です。
他にも心臓の交感神経の動きを調べるMIBG心筋シンチグラフィー、脳の動きを調べるダットスキャン検査、脳の働きを調べる脳SPECT・糖代謝PETなどが代表的です。
他の病気ではないかを判断する際などにも役立つ検査です。
レビー小体型認知症の症状を緩和させる方法
レビー小体型認知症に対する根本的な治療法はまだ見つかっていません。ただ、薬を使用しない非薬物療法や、症状に合わせた薬を用いる薬物療法などで症状を緩和させることは可能です。
たとえば、非薬物療法では、脳を活性化させるデイサービスに通うのも良いとされています。特にレクリエーションなどを通して楽しく脳の活性化ができれば、患者さん本人にとっても良いといえるでしょう。
また、ストレッチやウォーキングなどの運動療法は、パーキンソン症状の緩和にも効果的です。身体を動かすことは脳への血流改善にもつながります。
部屋が暗いと幻覚が見えやすくなるため、照明を明るくすることが効果的です。
また、万が一転倒したときのことを考え、自宅では足元を歩きやすい状態にして危ないものは片付けておくことも大切です。
薬物療法では、パーキンソン症状や不眠など、それぞれの患者に応じた薬が処方されます。ただ、レビー小体型認知症の場合は抗精神病薬に過敏になることがあるため、服薬管理や、担当医師への相談を欠かさないことが大切です。
施設選びや介護にお悩みのかたはお気軽にご相談ください。
介護相談のプロがあなたのお悩みに寄り添い、最適な施設をご紹介いたします。
周囲の支えも必要
いかがだったでしょうか。レビー小体型認知症の概要や症状、セルフチェックリストなどを紹介しました。どのような病気なのかについてご理解いただけたかと思います。
特に症状が進行すると、周囲のサポートは欠かせません。
有料老人ホームスーパー・コートでは、パーキンソン病などの神経難病の方に特化した介護施設ご用意しています。また、認知症の方にとっても専門的な会話・ケアを提供しているので、レビー小体型認知症と診断されてしまった方も一度ご相談ください。
監修者

花尾 奏一 (はなお そういち)
介護主任、講師
<資格>
介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
<略歴>
有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。