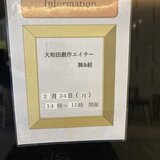こんにちは♪こんばんは♬
せいりょう姫島のブログをご覧頂き誠にありがとうございますm(__)m
明日1月7日は、「七草粥」の日ですね(^^♪
七草粥を食べる前に、由来や期限について色々知って頂けたらと思います。(^O^)
七草粥と深い関係にある「節句」を皆さんはご存じでしょうか?
起源・由来
1月7日(人日:じんじつ)・3月3日(上巳)、5月5日(端午)、7月7日(七夕)、9月9日(重陽
:ちょうよう)この五つを合わせて「五節句」と呼びます。
1月7日は1年で最初の節句になります。「人を大切にする。」という意味で「人日」という節句で
す。
唐の時代、人日の日には七種類の野菜が入った汁(七種菜羹:なんしゅさいのかん)を食べて、無
病息災を願っていたそうです。
日本には、平安時代に伝わって来ました。元々日本にあった「若菜摘み」という風習が合わさって、
七草粥を食べる文化がひろまっていきいきます。
時は流れ、江戸時代になると、幕府が人日の日のことを「人日の節句」として、1年間のイベント
として取り入れたことにより、1月7日に七草粥を食べる文化が確立されたみたいです。
※諸説あります。
食べる理由
七草月を食べる理由は、「無病息災」・「長寿健康」の2つがあります。
青菜の摂取が不足しがちな時期に、しっかりと体に取り入れる。お正月のごちそうで疲れた胃腸をい
たわるためという説もあります。
江戸時代は、寿命は短くどうすれば健康でいられるか?長生きするための生活とは何か?今よりも
医学等色々なことが分かっていない状態でも、「健康でいたい、長生きしたい」という意味を込めて
七草粥を食べていたことは、当時の日本人にとって「体に優しい」「健康的」な食事と考えられてい
たと思います。
種類
七草粥には、いわゆる「春の七草」と呼ばれる野菜や野草が入っています。
芹(せり)、薺(なずな)、御形(ごぎょう)、繁縷(はこべら)、仏の座(ほとけのざ)
菘(すずな)、蘿蔔(すずしろ)の七種類になります。それぞれの野菜には意味があり、健康を促す
効果が期待されています。
最後に、春の七草と呼ばれていますが、江戸時代と現代では暦が違う為、江戸時代の人日は現代で2月
上旬に当たります。その為、江戸時代の人々は七草を集めるのに大変苦労されていたと思います。
風習等を調べてみると、色々な事を知る事が出来ます(^O^)/
時間がある時に、気になる事を調べてみてはどうでしょうか。

















![IMG_3498[1].JPG](https://www.supercourt.jp/blog/himejima/assets_c/2025/02/8d19e144393aed975bb1c226df65efdcd2c4f43b-thumb-160x160-256780.jpg)